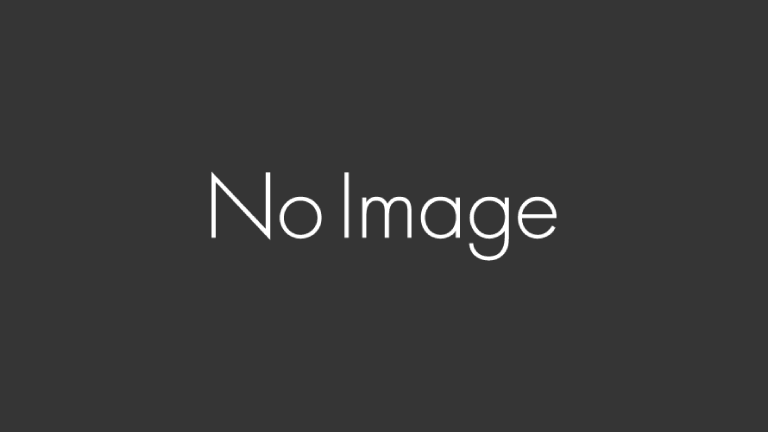被告人は、外国人風の男から改ざんテレホンカードを購入し、通話可能度数に関する磁気情報が正規の度数以上に改ざんされていることを知りながら、それをカード式公衆電話機に挿入して通話に使用した。右テレホンカードは、発行時の通話可能度数が50度であったが、何らかの手段によって105度にまで改ざんされ(押収時の可能通話度数は52度)、またテレホンカードの度数目盛の零度付近から数個のパンチ穴があけられ、裏面においてそのパンチ穴を塞ぐようにアルミ箔ようのテープが2枚(2〜3×32ミリメートルおよび2〜3×18ミリメートル)貼られているという外観上の異常性を有する改ざんテレホンカードであった。
検察官は、被告人を変造有価証券行使罪(刑法163条)で起訴したが、原審である千葉地裁は、使用済みテレホンカードの磁気情報部分の改ざんは新たな有価証券を作出する偽造行為であり、その使用については偽造有価証券行使罪が問題となるところ、本件テレホンカードは、未だ一般人をして真正に作成されたテレホンカードであると誤信させるに足りる外観を備えているとは認められないから偽変造有価証券にあたらないとして、変造有価証券行使罪ではなく、不正作出電磁的記録供用罪(刑法161条の2第3項)の成立を認めた(千葉地裁平成6年1月26日判決)。
NTT発行のテレホンカードが有価証券と解されるのは、テレホンカードの磁気情報部分と券面上の記載及び外観を一体としてみれば、電話の役務を受ける財産上の権利がその証券上に表示されていると認められ、かつ、これをカード式公衆電話機に挿入することに基づいている。したがって、テレホンカードの変造(偽造)に関しても、テレホンカードとしての電磁的記録の可能なカードに正規でない通話可能度数が記録されていることのほか、そのカード上の表示及び外観においても、一般人をして真正に作成されたテレホンカードと誤信せしめるに足りる程度のものでなければ、変造(偽造)の有価証券にあたるということができないのは、原判決も説示するとおりである。
本件テレホンカードは、NTT発行の通話可能度数50度数のテレホンカードの磁気情報部分に何らかの不正な手段を使って105度数が磁気記録されたものであり、カード上の記載等に手が加えられたりはされていない。ただ、外観上問題となるのは、本件テレホンカードには実際の通話可能度数の目安となる数字の辺りにパンチ穴が打刻されていること及びこれらのパンチ穴を塞ぐ形で2枚のアルミ箔ようのテープ(約2×32ミリメートル及び約2×18ミリメートル)が貼られていることである。したがって、通常人であれば、本件テレホンカードを手にした際に、右のようなパンチ穴や貼付されたテープに直ちに気づき、外形が毀損されているとみて、真正なカードに不正な手が加えられたものと考えるのが一般であるかどうかが問題となる。
本件テレホンカードについては、パンチ穴が開けられテープが貼られているとはいえ、NTTが正規に発行したものではないかという不信の念を抱かせるほどの外観の異常さは認められないから、変造有価証券にあたる1。(破棄自判・確定)
3. 1. 問題の所在
従来、下級審において結論の分かれていたテレホンカードの有価証券性について2、平成3年4月5日に最高裁がそれを肯定する判断をして以来3、テレホンカード上の磁気情報たる利用可能度数を改ざんする行為や改ざんテレホンカードでの通話行為に対して、それぞれ有価証券変造罪、変造有価証券行使罪が適用されるという形で実務上一応の解決がなされたといえる。ただし、右最高裁決定において問題となっていた事案は、50度数のテレホンカードの利用可能度数を1998度数に改ざんしたというものであり、判決文からみる限り改ざんされたテレホンカードの外観に異常がなかった事案であったが、最近出回っている改ざんテレホンカードは、いったん使用済みとなったテレホンカードの利用度数を改ざんするものがほとんどであり4、テレホンカードの通話利用可能度数目盛り付近に開けられているパンチ穴を塞ぐためにテープを貼りつけるなどの細工がほどこしてあり、具体的には程度の差があるとはいえ、何らかの外観上の異常性が見られる点で、右最高裁の事案と若干事情が異なる。
このような使用済みテレホンカードを改ざんする行為については、すでに名古屋地判平成5年4月22日5において、使用済みテレホンカードの利用可能度数を改ざんする行為は有価証券の「変造」ではなく「偽造」ではないか、このような外観上の異常性のある改ざんテレホンカードはそもそも偽変造有価証券にはあたらないのではないか、といった問題が提起されていた。本件原審判決もこの名古屋地裁判決と同様の結論に至っている。同種の事案であるにもかかわらず名古屋地裁判決および本件原審判決と本件判決とでは結論において全く異なった判断がなされている。これは、当該改ざんテレホンカードにおける外観上の異常性についての事実認定の相違であると考えられる。いずれも基本的には、最高裁決定が提示した線に沿って判断がなされている点では違いはない。ただ、本件判決の評価をめぐって、従来の議論を一歩踏み出したような主張がいくつかみられるので、本稿ではそのような主張について若干の考察を行いたいと思う。
3. 2. 改ざんテレホンカードの外観の異常性について
(1) 一般に、有価証券の偽変造の程度については、外形上一般人をして真正に成立した有価証券であると誤信させるに足りる形式を備えている必要があると解されている。この原則を外観上異常性の見られる改ざんテレホンカードにあてはめてみた場合、テレホンカードの有価証券性についてどのように考えるかによってその結論に相違が生ずる。
伝統的には、有価証券は文書の一種であると考えられ、類型的に要保護性の高い有価証券をとくに厚く保護するのが文書偽造罪の特別規定としての有価証券偽造罪であるとされてきた6。したがって有価証券性についても、その基本的な要件として一般の文書と同様に人に対する直接的な可視性・可読性が要求されてきたのであった。このような原則をそのままテレホンカードにあてはめた場合(「有価証券文書限定説」)7、テレホンカードの券面上の記載部分についての有価証券性は肯定されうる8が、権利が実際に化体しているのは券面上の度数表示ではなくむしろ磁気情報部分であり、この部分こそがテレホンカードにとって本質的であるとするならば、可視性・可読性に欠ける電磁的記録部分の有価証券性は否定され、磁気情報部分たる通話可能度数のみの改ざんは有価証券の偽変造にあたらず、カード式公衆電話機に対する使用も偽変造有価証券の行使にはあたらないとされる。改ざんテレホンカードの外観の異常性については、テレホンカードの有価証券性そのものが否定されるならば、そもそもこのような問題は生じない。
有価証券文書限定説に立った場合、テレホンカードの磁気情報部分のみを改ざんする行為やそれを使用する行為については、電磁的記録不正作出および供用罪(刑法161条の2)が成立することとなるが、同罪においては偽変造有価証券交付罪(刑法163条)におけるような交付行為を処罰する規定が存在しない。しかし、現実にはテレホンカードの偽変造行為やその使用行為を直接に取り締まることがかなり困難なために、改ざんテレホンカードの交付行為を規制する必要性は肯定されるだろう。そこで、テレホンカードそのものについて有価証券性を肯定しようとする見解が主張されるのである9。
まず、テレホンカードに化体された権利を現実に行使する際には基本的には電磁的記録部分が重要な意味を持つのであるから、その有価証券性については人に対する直接的な可読性は問題とならないとして、権利の化体性を中心に考え、テレホンカードの電磁的記録そのものに対して直截的に有価証券性を認める見解がある(「電磁的記録有価証券説」)10。本説からは、電磁的記録である通話可能度数のみを改ざんする場合であっても有価証券の偽変造にあたることになり、このような改ざんテレホンカードをカード式電話機に対して使用する行為は、テレホンカード本来の用法に沿った使用方法であるから偽変造有価証券の行使にあたるとされる。なお本説からは、いわゆるホワイトカード(券面上の記載や外観からテレホンカードとは判別できない白紙のカードであるが、カード式電話機の利用が可能な情報が印磁されたカード)であっても有価証券であるとされる可能性がある11。改ざんテレホンカードの外観の異常性については、当該カードが不正な改ざんテレホンカードであることが外観上明らかなものであっても、それによってカード式電話機での通話が可能となるならば、本説からは有価証券の偽変造が認められ、その外観の異常性は問題とならない。
電磁的記録有価証券説は、人に対する誤信可能性を全く考慮しないのであるから、有価証券偽造罪を可視性・可読性が問題となる文書犯罪の枠外に位置づけようとする立場である。これに対して、有価証券は文書の一部であるとの伝統的な理解の上に立ちながら、テレホンカード上の可視的・可読的な文書(券面上の記載・外観)とそうでない電磁的記録(通話を可能とする磁気情報)とが一体となって有価証券を構成すると解する立場がある(「一体説」)12。すなわち、有価証券は、通常は人に対して直接的に可視的・可読的な券面上の記載が問題となるのであるが、テレホンカードの場合にはカード裏面の電磁的記録がカード式公衆電話機を利用できる財産上の権利に関して券面上の記載を補充するものであるから、その限りで有価証券の一部分を構成する。したがって、券面上の記載には手を触れず、電磁的記録における通話可能度数のみを改ざんする行為も有価証券の偽変造にあたり、改ざんテレホンカードを電話機に挿入して使用する行為は偽変造有価証券の行使にあたると解するのである。前述のように、最高裁平成3年4月5日の決定において、実務上はこのような形で一応の決着がつけられたのであった。
一体説においては、電磁的記録を含めて券面上の記載をも有価証券を認めるにあたっての重要な要素と考えるのであるから、改ざんテレホンカードにおいても一般の有価証券と同様に、当該改ざんテレホンカードが外形上一般人をして真正なテレホンカードと誤信せしめるに足りる形式を備えていることが必要とされるだろう。したがって、外観上異常性の認められる改ざんテレホンカードが偽変造有価証券とされるかどうかは、具体的事案における異常性の程度についての事実認定の問題に還元されることになる13。そうすると、名古屋地裁判決と本判決のように改ざんの方法やその目的が同じであり、共にカード式公衆電話機において現実に通話が可能であるにもかかわらず、つまり機能的には全く同一のカードであるにもかかわらず、使用済みを示すパンチ穴の位置や数、またそれを塞ぐために細工したテープ等の些細な外観上の違いによって偽変造となる場合とならない場合とが生ずる可能性がでてくるのである。
そこで、このように改ざんカードの機能面からは全く同一でありながら、些細な外観上の相違によって結論が異なるということ対して根本的な疑問が提起されているのである14。(2) 名古屋地裁判決および本件原審判決は、従来から文書偽造罪において一般的に説かれていることをそのまま有価証券偽造罪にあてはめたものであり、有価証券が可視性・可読性を有する文書であることを前提とした議論であるといえよう。しかし、最高裁が、機械に対する使用をテレホンカードの行使と認めたことから15、テレホンカードについて人に対する誤信可能性要件の比重が全体として低くなったことは確かであり、当該改ざんテレホンカードがカード式電話機を作動させることが可能か否かというテレホンカードとしての機能面を重視する方向が開かれたといえる16。この方向を志向するものとして園部は、名古屋地裁判決が偽変造を否定した改ざんテレホンカードのような場合であっても、「それを使用してカード式公衆電話機で電話をかける可能性があり、また、それが流通して同様にカード式電話機で行使される可能性があるから、偽変造にあたると解する余地も十分にあるように思われる。」17という。小川も、改ざんしたテレホンカードがカード式公衆電話に挿入された場合、それがそのシステムに適合し、真正なカードとして受け入れられる場合には、右改ざんは有価証券の偽変造にあたると解するのが正当と思われる、と述べる。すなわち、「機械に対して使用することを端的に行使と解するのであれば、磁気情報部分以外の外観に一見明白な異常があっても、真正なものとして使用できるのであるから、有価証券の真正さに対する信用をそこなうおそれがあると解することができるのではあるまいか。このように考えると、改ざんしたテレホンカードがカード式公衆電話に挿入された場合、それがそのシステムに適合し、真正なカードとして受け入れられる場合には、右改ざんは有価証券の偽変造にあたると解するのが正当と思われる」18、という。このような見解は、外観上テレホンカードであることが認識可能であるかぎり、つまり、カード式電話機にそれが不正に使用される可能性があるかぎり、外観上異常性の程度が高く偽変造カードであることが認識しうるものであったとしても偽変造罪の成立を肯定するのであるから、明らかに一体説の範疇を越えるものであろう19。そうすると、いわゆるホワイトカードの扱いが当然問題となるが、「外観上何のカードか全くわからないようなものであれば、これを入手した者がカード式公衆電話機のシステム内で使用する可能性はほとんどないのであるから、外観に異常はあるがテレホンカードであることを識別できる場合とは異なり、有価証券にあたらないと解することも可能であろう。」20、という。
(3) 行使の点において人に対する誤信の可能性が考慮されず、外観上異常性のあるカードであっても、それがカード式電話機に対して使用される可能性があるかぎり有価証券偽変造罪の成立が肯定されるならば、改ざんテレホンカードが使用されることによって具体的に何が侵害されるのかが改めて問われなければならない。
一体説は、可視的・可読的な部分である券面上の記載・外観とそうでない電磁的記録部分とを後者が前者を補充するものとして位置づけて、両者を一体化させたわけであるが、それはテレホンカードの偽変造をあくまでも文書犯罪の枠内に位置づけようとしたものであると解される21。
この点をもっと明瞭に打ち出したのが、最高裁決定の原審判決である東京高判平成2年6月25日(刑集43巻2号83頁)であった。そこでは、電磁的記録としての利用可能度数は直接には可読不可能ではあるが、それはカードリーダーによって公衆電話機上に赤色表示され、間接的に可読可能であるという点が有価証券であることの根拠とされたのであった。公衆電話機のカウンターに表示される度数をテレホンカードの真正な権利内容であると一般人が誤信する可能性のあること、および変造テレホンカードの使用によって公衆電話の設置者であるNTTが欺罔されることが、「人を誤信させる」ことにあたると解されたのである。しかし、NTTに対する使用を人に対する行使と解するこのような間接的可読性説は、従来模造コイン等によって自動販売機から財物を引き出す行為や偽造CDを使用してATMから現金を引き出す行為が詐欺ではなく窃盗とされてきたことなどとの整合性から、一般には支持されなかったのであった。最高裁決定が、テレホンカードの有価証券性については一体説をとりながら、行使の目的の要件については人による誤信可能性を問題としなかったのは、このような点を配慮してのことであったと思われる22。しかし、行使から人の誤信可能性の要件を外したことから、有価証券偽造罪の罪質に異質なものが紛れ込んだおそれがあるのである。
有価証券制度の本来の意味は、権利が無形で抽象的なものであるから、それを一定の証券上に化体させて、権利の行使を確実なものにするという点に認められる。したがって、有価証券偽造罪の保護法益は、有価証券の成立の真正に対する一般の信頼を害するおそれのある行為を処罰することによって、経済取引の確実性を確保しようとするものであるといえよう。この点では有形偽造を処罰の原則とする文書偽造罪と構造的には変わりはない。しかし、このような理解と若干異なった理解も存する。たとえば前田は、有価証券偽造罪や偽造有価証券行使罪の保護法益を次のように説明する23。同罪の保護法益は、「有価証券や有価証券制度に対する国民の信頼」と、「当該証券の直接の関係者の利益」が「複合」したものである、という。そして、行使罪の場合には、の直接的な利益侵害の側面が重視され、の面の法益侵害性が強くなくともその成立が認められうるのである、という。ただし、真正のテレホンカードの外観を有する改ざんカードが多数出まわることは、のカードに対する信頼を大きく失わしめることは疑いないが、白紙のカードの流布はそれをあまり伴わないために、白紙のカードを作成しただけでは有価証券偽造とは評価されない。また、白紙のカードの使用は、の面の侵害に関しては印刷のあるカードの使用と大差がないが、ただ白紙のカードは「偽造有価証券」ではないので、その挿入行為に偽造有価証券行使罪の構成要件該当性が認められないのである、という。
有価証券偽造罪や同行使罪が保護しようとする利益の中には、「有価証券や有価証券制度に対する国民の信頼」と「当該の直接の関係者の利益」が「複合」的に含まれているといってもよいだろう。しかし、それはその他の社会的法益を侵害する罪、たとえば文書偽造罪においても同じであって、改ざんされた文書によって侵害される直接の関係者の利益侵害が大であるからといって、文書に対する社会的信用性に対する侵害が強くなくとも当然に犯罪の成立が肯定されてもよいということにはならない。有価証券の偽造や変造、行使等の行為は、有価証券の信用に対する抽象的危険のある行為として処罰されるのであり24、犯罪が成立するためには、有価証券の名義人や行使の相手方に具体的な財産的被害が生じることは必ずしも必要ではないが、逆に改ざんされた有価証券の行使によって具体的な財産的被害が生じるからといって、つねに有価証券の成立の真正に対する一般の信頼が害されるといいうるかは疑問である。前記のような立場は、有価証券の流通性よりもその行使性に重点を置く考え方であるといってよいが、確かに「通用」性(148条)や「流通」性(149条)を構成要件要素としている通貨偽造の罪と、そのような文言が使用されていない有価証券偽造の罪とでは事情が異なりうるだろう。しかし、通説・判例が定期乗車券のようなものに有価証券性を認めているとしても、それはたまたま流通性が欠けても権利の化体性の点から刑法上の保護を例外的に及ぼしていると考えるのが妥当であろう。さもなくば、流通性が全く考えられないホワイトカードも、カード式電話機がそれを正規のカードとして識別する限り原則的に有価証券とされる可能性がある。有価証券偽変造罪が成立するためには、やはり流通性を全く無視するわけにはいかないのであって、当該行為によって「有価証券や有価証券制度に対する国民の信頼」が動揺させられるということがなければならない。
それでは、改ざんテレホンカードの使用において侵害されるものとは何だろうか。現実には、改ざんされた磁気情報によって電話が作動し、設置者であるNTTの事務処理が阻害され、その結果財産的被害が生じるということであるが、そこにNTTの具体的な財産侵害という範囲を超えるものがあることは否定できない。しかし、それが、「わざわざテレホンカードを使わなくても通話できるなら、テレホンカードを使用することがばかばかしくなる」という形での一般の不信感であるならば、そのようなものを有価証券偽造罪の保護法益とすることはできないだろう25。そのような意味での公共的な不信感とは、実は改ざんテレホンカードによって通話が可能となってしまったカード式公衆電話機に対する機能的な面での信頼低下だからである。
通常の文書犯罪においては、「偽変造の文書が流通することにより、文書に対する社会的信用が害され流通が停滞することによって制度の維持が困難になることを予定するものである」が、改ざんテレホンカードの場合は、「発行者(テレカの名義人)たるNTTとの関係、すなわち対内関係で有害な行為ではありえても、文書犯罪の本質である対外関係、すなわち名義人以外の第三者の信頼を害するという要素には欠けるというべきであろう」26。それは、次のような事例を考えてみればさらに明らかになるであろう。
行為者によって、たとえば改ざんテレホンカードの表面に油性ペンで「偽変造カード」と書かれているような改ざんテレホンカードが作成され、第三者がそれを入手したならば、どのように判断されるのであろうか。わざわざ「偽変造カード」と書かれているカードを真正なものかもしれないと思う者はいない。しかし、そのようなカードを見た者は、それがカード式公衆電話機に対して使用可能であると容易に知ることができる。つまり、このようなカードを入手した者によってそれがカード式公衆電話機に対して不正に使用される可能性は、通常の改ざんテレホンカードと同様に高いであろう。それは機能的には真正なテレホンカードと同一であり、機械からは真正なカードとして受け入れられる。もしもこのような場合にも犯罪の成立を認めるとすれば、それは結果的には電磁的記録有価証券説に立たない限りその有価証券性が否定されているホワイトカードについても有価証券偽変造罪を認めることと変わりはないであろう27。一体説はテレホンカードの可視的・可読的部分に対する信頼を強調したのであるが、改ざんテレホンカードの機能面を強調することによって、結果的には電磁的記録有価証券説に移行してしまうことになるのである。
3. 3. 使用済みテレホンカードの改ざんは「偽造」か「変造」か
一般に有価証券の「偽造」とは、作成権限のない者が他人の作成名義を偽って真正な有価証券の外観を呈する証券を作成することであり、有価証券の「変造」とは、真正に成立した他人名義の有価証券の記載に権限なく変更を加えることであると解されている。したがって、既に効力を失った証券の記載を変更して有効な証券の外観を呈するものを作成する行為は、偽造罪にあたる。
名古屋地裁判決と本件原審判決では、このような原則がそのままテレホンカードに当てはめられて判断されている。すなわち、通話可能残度数がゼロとなったテレホンカードは、すでにテレホンカードとしての効力を失っているのであるから、使用済みのテレホンカードの利用可能度数を改ざんする行為は偽造行為となるとされたのであった。これに対して、本判決は変造としたが、その理由については特段触れられていない。実務的には、未使用・使用中・使用済みを問わず、テレホンカードの改ざんについては「変造」として処理することが通常であったと思われる。
改ざん行為が「偽造」か「変造」かについては、同一の罰条で規定されているのであるから、この問題は純粋に理論的な問題であるといえようが、考え方としては次のようなものがありうる。
改ざんされた証券になお権利が化体しているか否かによって偽変造を区別するもの。使用済みテレホンカードは、もはや電話の役務を受ける財産上の権利がカード上に化体されたものとは言いがたいから、使用済みカードの改ざんは新たなテレホンカードを作出するものとして「偽造」であると考える28。
有価証券としての存在を終えたものを不正に再生すれば「偽造」となるのであるから、使用済みテレホンカードにおいて使用可能度数の零度の位置にパンチ穴が開いていても、券面上表示された権利を化体するものとして社会から認識されなくなるとはいえないとして、使用済みテレホンカードの改ざんを「変造」ととらえる29。
偽造か変造かは証券上に権利が化体されているか否かという法的観点から区別されているものであるから、説が妥当と思われる。同一罰条で規定されている行為類型であるとはいえ、やはり理論的には使用済みテレホンカードの改ざんは「偽造」であると思われる30。しかし、そうすると個々の事案においてそれが「偽造」なのか「変造」なのかを区別することがかなり厄介な作業となることが予想される。通常は、大量の使用済みテレホンカードを改ざんする場合が多いであろうから、その1枚1枚について残度数が零度であったのか否かを調べなければならない。そこで説に立つ論者もこのような実務的処理の煩雑さを配慮して、実務における「変造」での処理を追認している31。しかし、このようなある意味では不透明な処理は、本来不可視的な電磁的記録の改ざんに対して、可視的な文書を前提とした偽変造の概念をあてはめようとすることがそもそも無理であることを示しているように思われるのである。
本判決は、外観上異常性のある使用済みテレホンカードの改ざんについて有価証券変造罪を認めたわけであるが、表面的にはあくまでも一体説を前提として「人に対する誤信可能性」の点についての事実認定が問題となっている。したがって、その異常性の程度が高い場合についての問題はなお残されているといえよう。最高裁決定の趣旨から言えば、異常性の程度が高い場合には偽変造有価証券ではないとするのが妥当であると思われるので、改ざんテレホンカードの機能面から偽変造を判断しようとする上記のような立場は少なくとも一体説とは符合しないのみならず、結論においても妥当ではないと思われる。しかし、一体説は、テレホンカード全体の有価証券性については人の誤信可能性を要件としながら行使の点においてそれを外したことから、内部矛盾をはらんでいるといわざるをえず32、その点において本判決は、実務上一応の決着をみたとされる一体説について再検討する契機となるものであろう33。
《注》
1 なお、「変造」と判断した理由については、特段触れられていない。
2 従来の下級審判例については、宮澤・平良木・島岡5、原田9(以下、末尾の《主要参考文献》欄の番号によって引用する)において詳しい分析がなされている。
3 最決平成3年4月5日(刑集45巻171頁)。事案は、被告人が通話可能度数50度のテレホンカードを通話可能度数1998度数のテレホンカードに改ざんし、この改ざんされたテレホンカードを、その旨を告げた上で売り渡したというものであった。最高裁は、次のような理由から、被告人の行為に有価証券変造罪、変造有価証券行使罪の成立を認めた。
テレホンカードの磁気情報部分並びにその券面上の記載及び外観を一体としてみれば、電話の役務の提供を受ける財産上の権利がその証券上に表示されていると認められ、かつ、これをカード式電話機に挿入するものであるから、テレホンカードは有価証券に当たると解するのが相当である。
昭和62年の刑法の一部改正によって電磁的記録に関する諸規定が新設されたが、電磁的記録を含むテレホンカードのようなものが有価証券ではないと確認されたわけではない。
有価証券の変造とは、真正に作成された有価証券に権限なく変更を加えることをいうと解されるところ、テレホンカードを有価証券に当たると解する以上、その磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為がこれに当たることは、明らかである。また、偽造等をした有価証券の行使とは、その用法に従って真正なものとして使用することをいうと解されるから、変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用する行為は、変造された有価証券の行使に当たるというべきである。
4 小川20−62頁以下参照。
5 判例タイムズ840号234頁。事案は、被告人が使用済みのテレホンカード17枚について、変造機械を用いて通話可能度数を540度数等とする電磁的記録を印磁して改ざんしたというものであるが、その際テレホンカード上の利用可能残度数を示す零度の記載位置等にパンチ穴が開いていたため、各カードのパンチ穴数箇所に黒色の磁気テープ(8×16ミリメートル程度)を貼りつけたというものであった。検察官は、有価証券変造罪により起訴した。名古屋地裁は、以下のような理由から有価証券偽変造罪の成立を否定して、私電磁的記録不正作出罪の成立を認めた。
使用済みテレホンカードにおいては、権利がすでに消滅しているのであるから、このようなカードを改ざんして権利が存在するかのような外観を作出する行為は、新たな有価証券を作出するものとして、偽造罪の成否を問うべきである。
改ざんテレホンカードについて有価証券偽変造罪の成立を肯定するためには、作出されたカードが、券面上の記載及び外観において、電話の役務を受ける権利を化体していると認識できるばかりではなく、一般人をして真正に作出されたテレホンカードであると誤信させるに足りるものであることが必要である。したがって、外観上、一見明白に不正に作出されたとわかるカードであれば、これを見た者が真正なテレホンカードと誤信するおそれはなく、それが社会に出回っても、NTTの財産的利益が害されることはあっても、社会一般のテレホンカードに対する信用が害されるおそれはない。
本件カード裏面に貼られた黒色テープは、色、大きさ、枚数からして極めて目立つものになっているから、本件カードを見た者の大半は、たとえ、カード式電話機で利用できるのではないかと思うにしても、同時に、通話可能性に関して不正な細工がなされていることを容易に推測すると考えられる。したがって、本件カードは、一見して正規のテレホンカードでないことが明らかなものであるから、一般人をして真正に作出されたテレホンカードと誤信させるに足りる外観を備えているとは認められず、被告人の本件改ざんは有価証券の偽変造罪に該当しないと解すべきである。
なお、本判決についての評釈としては、園部17、上嶌21がある。
6 岡田雄一『大コンメンタール刑法第6巻』186頁参照。
7 山口6−55頁以下、山中10−123頁、川端12−161頁、西田19−9頁以下、船山14−25頁以下参照。なお本説からは、とくに昭和62年の刑法一部改正において文書偽造罪に関して文書と電磁的記録とが明確に区別されたのであるから、有価証券偽変造との関連において文書と電磁的記録とを一体として考えることは不当である、という点が指摘されている。
8 テレホンカードは現実には譲渡性・流通性を有するのであるから、テレホンカードの外観を偽装して売却するような場合にまで有価証券性を否定する必要はないだろう(西田19−10頁参照)。
9 ただし、テレホンカードの有価証券性を認めると、法定刑がかなり重くなることには留意する必要がある。
10 古田2−44頁以下。
11 古田2−50頁。
12 大谷3−22頁以下、前田4−84頁以下、宮澤・平良木・島岡5(下)−168頁以下、岩崎8−19頁以下、原田9−147頁以下、岩崎11−160頁、木村16−260頁以下。
13 事実認定の問題としては、議論のあるところである。前田は、名古屋地判や千葉地判のように一般人の誤信可能性を厳格に解する必要性があるかは別個に検討を要するとして、「紙幣をはがして片面に和紙を貼っても通貨の変造」とした最判昭50年6月13日(刑集29巻6号375頁)を引用し、たしかにテープが貼ってあるが、それも片面のみであり、「『NTT』『利用度数』等の文字が印字され、外観上テレホンカードであることは明らかなのである」から、「『真正のテレホンカードと誤信するおそれがない』といいきることには無理があろう」とする(前田22−154頁以下)(小川20−65頁以下も同旨)。紙幣とテレホンカードは具体的な使用方法が異なるのであるから、同列には議論できなであろう(塩見23−38頁参照)。
14 前田22、園部17、小川20等。
15 電磁的記録の機械に対する使用を「行使」とすることについての根本的疑問として、宮澤・井田1−216頁以下参照。
16 原田9−147頁以下、前田15−196頁等参照。
17 園部17−32頁以下。
18 小川20−67頁以下。他に、岩崎8−19頁も同旨。
19 上嶌21−40頁、塩見23−38頁参照。
20 小川20−67頁以下。
21 西田19−8頁。
22 西田19−8頁以下。
23 前田4−88頁。
24 岡田・前掲187頁参照。
25 前田22−154頁。
26 西田19−7頁。
27 このことは単なるホワイトカード上にたとえば「カード式電話機に対して○度数使用可能」というように書かれている場合であっても同じことなのである。
28 小川20−69頁、園部17−30頁。
29 高崎18−19頁。
30 小川20−70頁、園部17−30頁。
31 小川20−70頁、園部17−30頁。小川・園部。ただ、技術的な点は不明ではあるが、使用済みを示すテレホンカード上のパンチ穴の位置と券面上に印刷された零度の表示について若干の位置的な誤差があり、改ざんの方法として(磁気テープが上から貼付されるような場合は別であろうが)テレホンカード上の古い磁気情報が改ざん情報によっていわゆる上書きされるような場合であるならば、改ざん前の当該テレホンカードの通話可能残度数に関する磁気情報を確認すること、つまり当該改ざんざん行為が「偽造」なのか「変造」なのかを事後的に確定することはそもそも技術的に不可能なのではないかという疑問は生じる。
32 西田19−9頁参照。
33 上嶌21−40頁、塩見23−38頁参照。《主要参考文献》(発表年順)
1. 宮澤浩一・井田良「銀行のキャッシュカードの磁気ストライプ部分が私文書偽造罪の客体に当たるとされた事例」判例時報1091号214頁(1983)
2. 古田祐紀「テレホンカードの磁気部分の度数情報を改ざんする行為と有価証券の変造」研修495号41頁(1989)
3. 大谷實「テレホンカードの改ざんと有価証券偽造の罪」研修499号19頁(1990)
4. 前田雅英「テレホンカードと変造有価証券交付罪」法学セミナー423号82頁(1990)
5. 宮澤浩一・平良木登男・島岡まな「改変テレホンカードと有価証券交付罪の成否(上)(中)(下)」判例時報1343号164頁、1346号164頁、1349号164頁(1990)
6. 山口厚「テレホンカードと有価証券変造」ジュリスト951号52頁(1990)
7. 伊東研祐「テレホンカードの通話可能度数記録を改竄し、これを売り渡す行為と有価証券変造罪・有価証券交付罪の成否」法学教室134号74頁(1991)
8. 岩崎義明「改ざんテレホンカードと有価証券変造罪の成否」研修516号13頁(1991)
9. 原田國男「1 テレホンカードと刑法162条、163条1項にいう『有価証券』、2 テレホンカードの磁気情報部分に記録された通話可能度数を権限なく改ざんする行為と刑法162条1項、163条1項にいう『変造』、3 変造されたテレホンカードをカード式公衆電話機に挿入して使用するこういと刑法162条、163条1項にいう『行使』」最高裁判所判例解説刑事編(平成3年度)114頁(1991)
10. 山中敬一「テレホンカードの不正使用と有価証券変造罪・変造有価証券交付罪の成否」法学セミナー442号123頁(1991)
11. 岩崎義明「テレホンカードの改ざんと有価証券偽造の罪」ジュリスト平成3年度重要判例解説159頁(1992)
12. 川端博「テレホンカードの有価証券性」刑法判例百選各論(第三版)160頁(1992)
13. 鶴田六郎「電子計算機使用詐欺罪が適用された1事例」研修532号13頁(1992)
14. 船山泰範「テレホンカードの変造と罪刑法定主義」日本法学57巻1号1頁(1992)
15. 前田雅英「変造テレホンカード事件上告審決定」判例時報1400号192頁(1992)
16. 木村光江「有価証券偽造罪–変造テレホンカードの問題を中心に-」刑法基本講座–各論の諸問題–254頁(1993)
17. 園部典生「使用済みテレホンカードの利用可能度数の改ざんについて有価証券変造罪の成立を否定して私電磁的記録不正作出罪の成立を認めた事例」研修544号25頁(1993)
18. 高崎秀雄「現代の犯罪とその方法上の問題点」法の支配93号19頁(1993)
19. 西田典之「テレホンカードと有価証券変造罪の成否−−最決平成3年4月5日(刑集45巻4号171頁)の批判的検討−−」研修537号3頁(1993)
20. 小川新二「利用可能度数を改ざんした使用済みテレホンカードを使用する行為と変造有価証券行使罪の成否について」警察学論集47巻12号56頁(1994)
21. 上嶌一高「改ざんテレホンカードの外観の異常と有価証券偽変造罪の成否」法学教室別冊・判例セレクト’94、40頁(1995)
22. 前田雅英「テレホンカードと有価証券の偽造」警察学論集48巻4号144頁(1995)
23. 塩見淳「有価証券(テレホンカード)変造の成否」法学教室別冊・判例セレクト’95、38頁(1996) 《追記》本稿は、平成7年度関西大学学部共同研究費による研究成果の一部である。