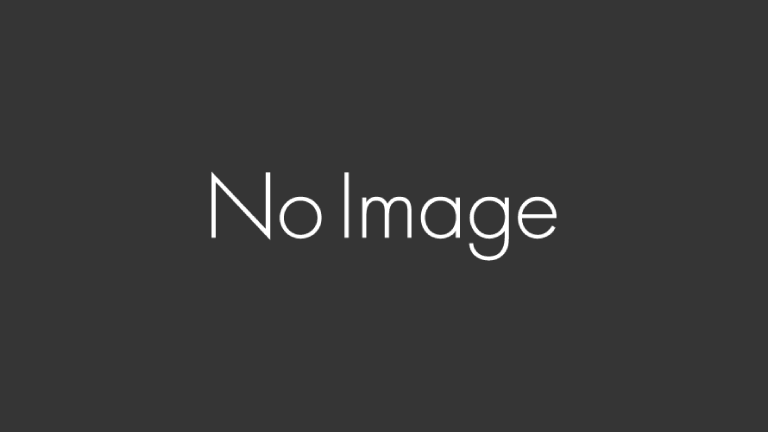以上の部分は、刑法の世界への導入部のようなものです。これから、いよいよ刑法の中心部分へと入っていきます。
ところで、ここまで読んでこられて、みなさんが今まで「犯罪」という言葉で描いてきたイメージが、だいぶ違ってきたことでしょう。もう気づかれたかと思いますが、私たちは実は「犯罪」という言葉を使って、二つのことを表現しているのです。一つは、「犯罪」という言葉で表現される、好ましくない事態であり、もう一つは、そのような事態を「犯罪」と評価する、私たちの評価行為です。事実そのものと事実に対する評価です。犯罪学と呼ばれる学問は、主として「犯罪」という言葉で表現されるような行為(事実)そのものを研究対象とするのに対して、刑法学は、事実に対する評価としての「犯罪」を問題とします。つまり、刑法学が研究対象とする「犯罪」とは、一定の規範的な評価を背負った事実であるということになります。
体系的思考
犯罪とは、極限状況において犯されるものであって、ドロドロとしたつかみどころのないものです。このような不確かなものを、そのままストレートに学問的議論の対象とするわけにはいきません。また、裁判で裁判官が直観的に、これは犯罪である、これは犯罪でない、という判断を行うならば、非常に危険なことです。そこで、対象となるモノをいくつかの要素に分解して、それを再構成するという方法をとります。
水を水素と酸素とに分解して、それを再合成して水を作るようなものです。ただし、水を水素と酸素とに分解して、その水素と酸素を再び化学的に合成しても、当然のことながら元の水と完全に同じ水ではありません。犯罪論体系においても、一応、犯罪をいくつかの要素に分解はしますが、この要素からもれていったものもたくさんあります。そのようなものを拾っていくことも、また重要かと思います。
「犯罪」というものをどのような規範的要素に分解するのかということは、国によって、また歴史によって違いがありますが、現在のわが国では一応構成要件該当性、違法性、有責性の三つの規範的要素に分解します。つまり、刑法的な犯罪の定義とは、「構成要件に該当して、違法かつ有責な行為である」となります。
体系論的な議論は、学問体系の命として、当然、体系内の論理的整合性を要求します。しかし、犯罪論体系の一つの目的は、犯罪の認定に統一的原理を提供して、(もちろん一般の人びとや警察官なども犯罪を認定するわけですが)最終的には裁判官をコントロールするという点にあります。専門的な議論では、体系内の論理的整合性を要求するあまり、ともすれば議論のための議論ということもなきにしもあらずですが、犯罪認定の統一的原理を提供するという犯罪論体系の使命を忘れてはならないと思います。
構成要件該当性
XがYに全治一週間の傷を与えたとします。理由はどうあれ、Xが行った行為それじたいを客観的に観察しますと、それは、刑法204条の傷害罪における「人の身体を傷害した者は・・・・・・」にあたります。Xという人が何らかの行為を行って、それが原因となって、Yが傷害を受けた。つまり、事実的な関係としては、Xの行為とYの傷害という結果との間には、原因・結果の関係(因果関係)が認められます。因果関係が認められるということは、客観的にYの傷害がXのせいであるとして、Xの行為に帰属させることができるのです。
このようにして、まず、Xの行為は人の健康に害を及ぼす、放置できないほどの重大な行為(傷害)であるという評価がなされます。最初の方で述べましたが、いかに重大な行為であっても、この刑法の条文に当てはまらない行為は犯罪ではなく、したがって、その場合には観念的にも事実的にも国家の刑罰権は発生していません。これは、罪刑法定主義からの当然の結論ですねっ。
一般に、刑法というものは、他の法律に比べて特殊な形をしています。条文を見れば分かりますが、刑法の条文の構造は、「〜した者は〜に処する」というような形になっています。この「〜した者は」という部分を構成要件といいます。
もともと構成要件という概念自体は、ドイツの刑法学から日本に輸入されたものですが、現在ではしばしば判例においても用いられ、わが国の刑法学の共有財産となっています。しかし、この概念に何を盛り込むのかという点については、たいへんな論争があります。極端なことを言えば、10人の刑法学者がいれば10人とも構成要件という言葉を用いて違ったことを考えている可能性があります。
前にも言いましたように、現実には傷害という形態はさまざまなものがあります。立法者は、それらの行為に共通するものを取り上げて、抽象的に類型化して「人の身体を傷害した者は」という形にまとめあげたわけです。ですから、構成要件を、犯罪とされうる行為を類型化したものという意味で、犯罪類型と考えても結構ですし、あるいは構成要件において類型化されている行為は、すべて刑罰の対象となるものです。国家は、これこれの行為をした場合には処罰しますよ、という形でそのような行為を禁止しているわけです。したがって、構成要件を禁止の素材あるいは禁止の内容と理解してもかまいません。とりあえず、ここでは、刑法の条文の前の部分が構成要件であると理解しておいていただければ、結構かと思います。ともかく、このような意味で、ある行為が構成要件に該当するということが、問題の出発点となります。犯罪行為に対する規範的評価の第一の要素は、「構成要件該当性」ということなのです。
違法性
ある行為が構成要件に該当しても、それだけで直ちに犯罪と評価され、具体的な刑罰が科せられるわけではありません。XがYを傷害したとしても、現実には、Yの方から先に先制攻撃をしかけ、それに対してXが反撃したのかも知れません。刑法36条には、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」という規定があります。これを正当防衛といいます。したがって、Yが不意にXを襲ってきたので、Xが自分の生命を守にためにYを傷害したというのであれば、処罰されないことになります。
問題は、何故処罰されないのかということですが、形式的に言えば、これはYの行為が違法であって、Xの行為が適法だからです。違法とは形式的には、法に反するということですが、実質的には法益を侵害するということです。この場合は、YはXに攻撃をしかけることによって、自ら自己の身体に関して法の保護を放棄していると考えることができます。Xは、この場合には何らの法益をも侵害していないのです。法文で「罰しない」と書かれているのは、このような意味です。
客観的にXの行為は刑法204条の構成要件に該当するわけですが、違法性が欠けるために結果的に犯罪ではなくなります。したがって、犯罪行為に対する規範的評価の第二のものは、「違法性」ということになります。
有責性
一般に「責任」という言葉を使います。「子供に対して親としての責任がある」とか、「そのことの責任をとって辞任します」、といったような言い方をします。前の方は、何かを引き受けてしなければならない義務という意味であり、これに対して後の方は、何か悪い結果を引き起こした場合に、その損失などの責めを負う、というように、同じ「責任」という言葉であっても、若干のニュアンスの違いがありますが、いずれも自分と全く無関係の事柄であれば、だれも「責任」を感じることはありません。しかし、何らかの事実的な関連性があれば、私たちは上に述べたような意味での「責任」を感じます。そして、かつてはこのような事実的な関連性だけで刑罰を科していた時代があったのです。結果の発生があり、それと因果関係がありさえすれば処罰されていました(結果責任)。しかし、現代ではこのような考え方は否定されています。
たとえば、AとBが格闘して結果的にBが死亡したのだけれども、Aは決してBを殺すつもりはなかった。あるいは、自動車を運転していて、誤って人を死亡させてしまった。このような場合に、行為者の結果についての主観的な関連性を一切無視して、人の死亡という重大な結果が発生しており、その行為と結果との間に因果関係があるという、ただそれだけのことで、すべて殺意のある通常の殺人の場合と同じように処罰するならば、刑罰というものは非常に残酷なものとなります。
したがって、人を処罰するためには、結果に対する事実的な関連性のほかに、主観的な関連性を吟味する必要がでてくるわけです。これを刑法の世界でも責任といいます。しかし、その意味は、上で述べた一般的な用い方とは少し違います。その違いを窃盗の例をあげて説明しましょう。
MがNの財布を盗んだとします。この時のMの心理状態はどのようなものでしょうか。まず、MはNの財布を盗むことを決心します。Nに近づき、手をのばす。Mには、自分が今からNの財布を取るのだということは充分に認識できています。このような事実を認識すれば、通常は行為者は規範の問題に直面することになります。つまり、Mが今から行おうとしている行為は、「盗み」という悪い行為であって、普通はここから「そのような行為は止めるべきである」という良心の声が聞こえてくるはずなのです。冷汗が流れ、たぶんMの心臓は通常の何倍ものスピードで、全身に血液を送り込んでいることでしょう。しかし、現実には、Mはそのような規範に直面し、その抵抗に遭遇したにもかかわらず、その制止を押し切って、Nの財布を盗みました。ここにMが非難される点があります。つまり、自分の行為を悪いものだと知っていながら、また、これを止めることができたにもかかわらず、あえて犯罪を実行したのです。適法な行為を行いえたにもかかわらず、何故あえて違法な行為を行ったのか、という非難が成立するわけです。良いことと悪いこととの判断がつかず、自分の行為の意味すら分からないような子供であれば、このような非難はできないですね。このような非難可能性のあることを「責任」といいます。
なお、責任の形式としては、故意と過失とがあります。故意というのは、知りつつ悪いことをする場合で、規範を直接破る場合です。過失というのは、前方不注意で事故を起こした場合のように、よく注意すれば結果の発生を避けることができたという状態、つまり、間接的に規範を破る場合です。もちろん、規範を意識して、それを直接破る場合の方が重く処罰されます。殺人と過失致死の刑罰の違いも、この点から説明することができます。
以上から、犯罪という規範的評価の第三の要素は、非難可能性があるという評価、つまり、「責任」という主観的評価であるということになります。
以上で、犯罪論体系の骨格は理解できたことと思います。「構成要件に該当して、違法かつ有責な行為」、これが刑法の世界における犯罪の定義なのです。これら三つの要素の中では、構成要件該当性の判断がもっとも広く、違法性・有責性となるにつれて、そこに取り込まれる行為の範囲が狭くなっていきます。つまり、人間の行為を段階的重畳的に評価して、犯罪の認定を慎重に行うわけです。ただし、構成要件と違法性の判断、構成要件と有責性の判断のそれぞれ相互の関係については、論争があります。
私たちが一般に何かをしようとする場合には、次のような段階をへます。まず、何かをしようとする決意があり、そのために準備を行い、実際にその行為にとりかかり、それを仕上げる。犯罪を犯す場合も同じです。たとえば、強盗を犯すことを決意し、そのためにナイフを用意し、現実に被害者を脅し、お金を奪う。つまり、決意→予備→着手→既遂という段階を踏むわけです。
決意
単に犯罪を決意しただけでは、決して処罰されません。それは、純粋に道徳の世界のことであって、刑法の世界の問題ではないからです。犯罪とは、構成要件に該当して、違法・有責な行為なのです。ただ、動機の形成過程については、さきほどの責任の評価や具体的な量刑に影響する点は否定できませんが、決意そのものは決して刑罰の対象とはならないのです。
予備
予備とは犯罪の準備活動のことです。とくに重大な少数の犯罪に限って、刑法はこの予備を処罰しています。重大犯罪については、できるだけ早い段階で阻止しようという発想ですが、具体的にこの予備罪を適用するとなると困難な問題が生じます。たとえば、殺人のためのナイフを購入するという行為は予備にあたりますが、デパートでナイフを物色している段階では予備罪にはあたりません。その限界をどうするかですが、判例では「その犯罪の実行に着手しようと思えばいつでもそれを利用して実行に着手しうる程度の準備が整えられたときに、予備罪が成立する」としています。
未遂
構成要件に書かれてある行為を実行行為といいます。「殺す」とか、「窃取する」、「傷害する」という行為です。この実行行為を開始することを、「実行に着手した」といいます。そして、実行に着手したが、結果が発生しなかった場合を未遂犯といいます(刑法43条「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。」)未遂の段階で処罰されるのも、重大な犯罪に限られています。
たしかに、刑法における処罰は、法益現実的な侵害があったということが原則で(既遂類型)、未遂の場合には現実的な法益の侵害が存在しません。しかし、たとえば顔のすぐ横を弾丸が飛んでいったというような事例を放置できるでしょうか。このような場合、私たちは、「ああ、助かった」と、胸をなでおろすでしょうが、これは裏を返せば、生命に対する具体的な危険を感じたということでしょう。そして、このような具体的な危険が実現されたということが、未遂を処罰する根拠であるといえます。この未遂犯においても、具体的にいつから実行に着手したといえるのか、ということが問題となります。
Aが、入院中のBを毒殺するつもりで、その病院に侵入しました。この段階で発見され逮捕されたとしても、生命に対する具体的な危険はまだ実現されていませんから、まだ殺人未遂ではありません。Bの病室を捜しあて、寝ているBに近づき、ポケットから青酸カリを取り出しました。この段階では、Aは殺人未遂であるとする考え方もあるかも知れませんが、一般にはまだ実行の着手ではありません。いよいよ、Aは、青酸カリをBの口の中に入れようとしました。この段階こそが実行の着手です。
これ以後は、偶然的な障害さえなければ、因果の流れはまっすぐにBの死へ向かって進展します。したがって、そのときにBが目を覚まして悲鳴をあげたために、Aが計画を放棄して逃走したとすれば、殺人未遂となります。
不能犯
上の場合に、かりにAがBを毒殺するということを事前に察知したCが、Aの青酸カリを砂糖とすりかえていたとしましょう。毒殺するつもりのAは、実はまったく無害の物質をBに飲ませようとしたわけです。殺人という結果は絶対に発生しません。しかし、Aは殺人を犯す意思で行為しています。Aは、殺人未遂となるでしょうか。
この場合は、一般の人がAの行為を見たとすれば、砂糖と青酸カリは似ていますので、やはり危険を感じるでしょう。Aがその物質を砂糖と知って、砂糖を使ってBを殺そうとしたという場合とは根本的に違うのです。この場合は、一般の人びとは、その行為からは生命に対する何らの危険も感じません。このような事例は、不能犯といって、当然不処罰になります。つまり、死の結果を発生させる可能性がある行為が実行行為なのであって、不能犯とされる事例では、実行行為そのものが存在しないのです。
人間は、さまざまな感覚器官によって外界の情報を収集し、それを経験則に照らして物事を判断します。しかし、人間の情報収集能力には限界があります。すべてを見通している、神のような存在からは必然と思われることでも、認識能力に限界のある人間にとっては未知の現象となります。ある意味では、危険とは、人間の無知の中に存在するものであるといえるのではないでしょうか。
Aが、警察官のピストルを奪って、Bに向かってそのピストルのひき金を引いた。しかし、たまたまそのピストルには弾丸が入っていなかった。弾丸が入っていないということを知ってるいる者にとっては、このAの行為は、何ら生命に対する危険な行為ではありません。しかし、普通は警察官の持っているピストルには、弾丸が装填されていると思いますよね。
刑法で規定されている犯罪は、単独犯でかつ既遂であることが原則です。しかし、現実には複数の人間で犯罪を犯すことが可能です。これを共犯といいます。刑法は、共犯の形態として共同正犯(刑法60条)、教唆犯(刑法61条)、そして幇助犯(刑法62条)の三つの形態を規定しています。
共同正犯
実行行為を自ら行った者を正犯といいますが、共同正犯とは、二人以上の者が共同して犯罪を実現する場合で、そのそれぞれが正犯として処罰されます。たとえば、AがCをピストルで脅迫している間に、BがCのポケットから財布を取ったとします。強盗罪です。AとBとが行った行為を分離して考えますと、それぞれ脅迫行為と窃盗行為となりますが、AとBは分業して犯罪を実行したのです。Aの脅迫行為がなければ、BはCの反撃を受けて財布を取ることはできなかったでしょう。また、Aにしても、Bの行為がなければ強盗を実現することはできなかったでしょう。このように、AとBは強盗罪の実現について必要不可欠の行為を行っているのです。各自が手を引けば、ただそれだけで強盗という全体の結果を失敗させることができます。したがって、強盗という全体から見れば、それぞれ部分的な行為しか行っていなくても、犯罪的意思を連絡して、実行行為を共同して行えば、全体の結果の責任を問われるのです。これを「一部行為の全部責任の原則」といいます。条文では、「すべて正犯とする。」と規定されていますが、それはこのような意味なのです。
ただし、判例は、意思の連絡さえあれば、たとえ実行行為を共同にしなくても共同正犯として処罰される場合があることを認めています。これを共謀共同正犯といいますが、学説の多くは従来からこの理論には否定的です。
狭義の共犯
教唆犯と幇助犯とを、共同正犯に対して狭義の共犯といいます。教唆とは、人を犯罪へとそそのかすこと、幇助とは、他人の犯罪を手助けすることです。共に、他人を介して法益を侵害している点では変わりありません。つまり、法益侵害に間接的な関連性があるということで、共犯が処罰されているわけです。しかし、教唆犯は、犯罪意思のない人を犯罪へとそそのかす場合ですから、新たな犯罪者を作り出すものであり、幇助は、既に犯罪を決意している人の犯罪実現を援助するという違いがあり、その犯罪性の違いから、教唆犯は正犯と同じように処罰されますが、幇助犯は、正犯について規定してある刑罰の半分の刑で処罰されます。
ところで、正犯とは実行行為者のことですから、正犯は他に偶然的障害さえなければ、直接的に法益を侵害するような行為を行っています。これに対して、共犯は、結果との間に他人の行為を介在させているのが特徴です。
AがBに対してCを殺すように教唆した場合、AはBを利用してCを殺害するのです。Bはもちろん独自に物事を判断し、決断する能力があります。BがAの申出を断る可能性もありますし、Bが殺人をいったん承諾しても、その決意を翻す可能性もあります。ここから、Aが自ら殺人行為を行う場合に比べて、Aが行う教唆行為は、殺人という結果に対しては実現の可能性が低い行為であるということができます。したがって、AはBに対してCを殺すように教唆しただけでは処罰されないのです。正犯たるBが、殺人の実行行為に着手してはじめて、共犯たるAの可罰性が生じてきます。このことを共犯の(実行)従属性といいます。
これに対して、共犯の独立性を主張する見解もあります。AがBにCの殺害を教唆しただけでAは処罰される。つまり、この見解は、共犯の行為が刑法43条の意味における「実行行為」であると考えるわけです。しかし、さきほども言ったように、実行行為とは、法益侵害を必然化するような行為と考えるべきですし、共犯行為は、他人を介在させている点において、この資格に欠けるものであるというべきだと思います。