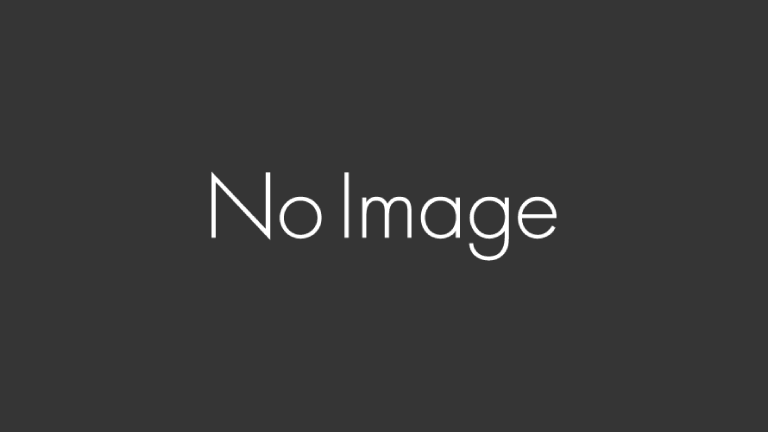かつて、多くの精神障害者は自宅で「鳥かご」のような場所に監置され、治療を受けることなく監禁されていた。昭和25年に成立した精神衛生法は、精神障害者の医療および保護を目的とし、このような悲惨な私宅監置制度を廃止し、入院中心の医療体制をとるものであった。しかし、入院中心の医療体制では、患者の人権救済が不充分であることが意識され、精神障害の早期発見・治療、社会復帰、アフターケアという一貫した医療体制の確立が叫ばれた。施設内治療から社会内治療、すなわち地域精神医療体制を前提とした新たな法制度の必要性が説かれたのである。
かつて、多くの精神障害者は自宅で「鳥かご」のような場所に監置され、治療を受けることなく監禁されていた。昭和25年に成立した精神衛生法は、精神障害者の医療および保護を目的とし、このような悲惨な私宅監置制度を廃止し、入院中心の医療体制をとるものであった。しかし、入院中心の医療体制では、患者の人権救済が不充分であることが意識され、精神障害の早期発見・治療、社会復帰、アフターケアという一貫した医療体制の確立が叫ばれた。施設内治療から社会内治療、すなわち地域精神医療体制を前提とした新たな法制度の必要性が説かれたのである。
法改正の直接のきっかけになったのは、昭和59年に発覚したU精神病院事件である(同病院における患者の過剰収容や無資格診療、無許可解剖、さらには看護職員の暴行による患者2名の死亡など)。この事件を契機に国内外から日本の精神医療体制に対する批判が高まり、それまでの精神障害者に関する総合的な法律であった精神衛生法の改正が行われた。昭和62年に成立した精神保健法は、現在の精神医療における大きな転換点となった。改正の理念は2つ、「精神病院から社会復帰施設へ」という流れを形成することと、患者の人権保護の強化である。具体的には、入院時の告知、定期病状報告、患者の退院・処遇改善請求およびそれを審査する第三者機関である精神医療審査会制度などの創設である。その後、精神保健法は平成5年に一部改正され、また同年の障害者基本法の制定によって精神障害者が同法の「障害者」とされて福祉対策の対象として明記されたことにより、平成7年には名称も精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)となり、医療と福祉の2本の柱からなる法体系へと改正されたのであった。さらに、本年2月、精神保健福祉法の改正要綱案が発表され、従来から問題となっていた、(1)医療保護入院対象者の明確化、(2)精神保健指定医の職務の適正化、(3)精神医療審査会の職務強化、(4)保護者の自傷他害防止監督義務の廃止など、かなり重要な改正が予定されている。
このように精神障害者に関する医療は、医療本来の領域から福祉の領域にまで広がり、精神障害者に対する人権への配慮が強く意識されているのである。 しかし、現実には法の理念が精神医療の現場の隅々にまで行き渡っているとは決して言えないような、前医療的な不祥事が今も跡を絶たないのはなぜか。

昨年5月、新潟県のS病院精神科病棟で、入院中の女性患者が体を拘束された状態でおう吐物をのどに詰まらせ窒息死するという事故があった。事故じたいについての法的責任は別として、問題はこれが構造的なものであったということだ。 新聞報道(1998年9月25日毎日新聞)によれば、拘束は、指定医の診察がないまま、看護婦の判断で行われていたという。県の調査によれば、S病院では死亡事故以外にも、7月末までの1年間に、精神保健福祉法や厚生省令の手続きに反した疑いのある拘束や隔離などが26件あったことが判明し、県はS病院に処遇改善命令を出した。処遇改善命令の内容は、(1)拘束は、必ず医師が患者を直接診察して、必要と認めた場合に限る、(2)この場合、診療録に記録する、(3)隔離を行う場合も診療録に記録する、というごく基本的な内容であった。 また、昨年の8月には、鹿児島県のA病院で、看護婦3人が暴れた入院患者を抑制するため、庭の立ち木に縛り付けるという事件も報道されている。新聞報道(1998年11月5日朝日新聞)によると、閉鎖病棟に入院中の50歳代の女性患者が暴れだし、同室の女性患者に暴行をはたらいたため、当直の看護婦3人が止めようとしたが収まらず、中庭に連れ出した。暴力をやめるよう説得したが、大声を出すのをやめないため、立ち木を抱かせ、両手首を布の帯で縛ったという。縛った時間は7〜8分間で、患者の状態が収まったため、自室に連れ戻し、睡眠薬を与えて眠らせた。看護婦は病棟日誌に患者を木に縛ったことなどは記録せず、当直の指定医にも報告していなかった。この患者は月に2〜3回同室の患者に暴力を振るうことがあったので、当直時間帯に暴れてほかの患者にけがを負わせる危険があるような場合には、看護婦が保護室に入れ、すぐに医師に連絡することになっていた。しかし、この時は16室ある保護室が満員だったため、看護婦の判断だけで患者を拘束し、木に縛り付けたという。 患者の治療に当たって、法律の個々の条文を念頭において治療に当たる者は多くはないであろう。しかし、強制的措置が行われる場面での手続きについての意識は重要である。木に縛りつけるというのは医療以前の人道的問題であるが、法が規定する手続違反であってもそれがさらに重大な人権侵害につながる可能性は高い。精神医療のもつ、潜在的な人権侵害の可能性にはつねに留意すべきである。

一部の病院で明るみになったこのような事件をきっかけに、精神医療の現場に対する法的規制が強化されることについては、反対する意見も当然予想される。法の介入はできる限り最小限であるべきだという意見も理解できないわけではない。しかし、上述のようなことは決して一部の病院での出来事ではなく、現在の精神医療そのものに内在する構造的な問題であるといえるかもしれないのである。別の新聞報道(1999年2月17日読売新聞)は、さらに次のようなショッキングな記事を伝えている。 厚生省の立入り調査によって、精神病治療が専門の18の国立病院のすべてで、入院患者に対し違法な処遇が行われていることが判明した。隔離患者222人中、手続きが適正だったのは157人。残りの65人には、精神保健福祉法に違反する処遇が行われていたという。指定医の診察・指示がないまま、看護職員の判断だけで隔離されていた患者が10人、指定医の指示なしに12時間以上隔離された患者も5人いた。精神保健福祉法は、隔離患者を医師が毎日診察するよう規定しているが、7人には守られておらず、カルテに診察内容などの記載漏れがある患者も32人いた。また、隔離はされていないが、治療上、身体的拘束を受けている88人の患者のうち、37人に違法処遇があったと記事は報じている。 形式的には手続違反である。しかし、強制的措置を施す場合、その最低限の正当性を担保するのはまず手続的な合法性なのである。もちろん医療の中身が問題なのであるが、どんなに有効でかつ患者本人の福利につながる医療であっても、法の定めた手続きを踏まない医療は違法といわざるをえない。もしも、病院関係者が「単なる手続違反」との認識をもっていたとすれば、その認識のズレこそ問題とされなければならないであろう。 精神医療が精神医学の専門的知識および医学的な準則に支えられて実施されるべきであることは、他の一般医療と何ら異なるところはない。しかし、精神医療は、他の一般医療以上に多くの法律によって規制を受けている領域でもある。とくに入院の要否に関する判断、病院内での行動規制の具体的な方法・程度など、精神医療に法が介入する範囲は広い。医学的診断や治療については、本来医師がみずからの責任で行うべきものであって、なぜそれが法的規制を受けなければならないのかについて、根本的な疑問をもつ医師も少なくはないであろう。しかし、なぜ法が精神医療に介入しなければならないのかを改めて意識することが出発点であると思われるのである。

精神医療に何らかの強制力が伴わざるをえないことは、法も認めるところである。精神医療に伴う強制医療を正当化する原理としては、ポリスパワー(police power)思想とパレンスパトリエ(parens patriae)思想とが対比して説明される。ポリスパワー思想によれば、自らの行動について制御能力を欠く精神障害者は、社会の安全のためにその将来の危険性を予測して強制的措置を講じることが許される。つまり、強制医療の根拠は精神障害者のもつ潜在的な危険性あるいは脅威であり、この危険性は犯罪と同様に厳格な手続のもとに認定されなければならない。厳格な手続的ハードルをクリアした者に対してのみ強制的措置が可能であると主張した(リーガルモデル=legal model)。これに対して、パレンスパトリエ思想は、精神障害者には自ら決定する能力が欠如しているのであるから、本人に代わって社会が彼らにとって最良の医療を選択し、決定しなければならないとする。この立場からは、精神障害者に対する医療の原則は、医療的な立場から患者本人にとっての福利を最高の原理として医療保護を実施すべきであるということになる(メディカルモデル=medical model)。 ポリスパワー思想は、1960年代から70年代にかけて欧米で強力に主張されたもので、精神医療の分野にも憲法上の適正手続の要請を導入するものであるから、精神障害者の人権保障に貢献したことは事実である。しかし、反面慢性かつ重度の精神障害者を必要な医療から遠ざけたこともまた事実であった。さらに、根本的に、強制的治療を正当化するだけの犯罪的危険性を事前に判定することは不可能であり、仮にそれが予測可能であるとしても、法秩序が一般人に対する予防拘禁を認めていない以上、犯罪的危険性を根拠に精神障害者についてのみ事前拘束を認めるのも理由がない。このような問題点から、現在ではポリスパワー思想は衰退し、精神障害者の福利に最高の価値に置くパレンスパトリエ思想が有力になっているのである。 国民の生存権・健康権を保障し、国に努力を促す憲法25条の趣旨からすれば、社会的適応能力が不十分な精神障害者に対しては、患者本人の福利のために一定の強制的な医療を施すことは基本的人権の侵害には当たらないと考えられる。それどころか、精神障害のために適切な自己決定ができない者に対して、国や社会が医療保護を加えることは、精神障害者の幸福追求権を保障するものとしてむしろ国の責務ですらある。かくして、強制的な精神医療は、基本的にはパレンスパトリエ思想によって根拠づけられる。 しかし、ポリスパワー思想を否定することから、リーガルモデルの発想までも否定すべきではない。ポリスパワー思想を否定したとしても、精神医療に不可避的に伴う潜在的な人権侵害的性格までも払拭することはできないからである。精神病院の不祥事が跡を絶たないという事実は、それを証明しているように思われる。およそ人の自由を強制的に奪う措置を施す以上、そこにはつねにその強制が不必要かあるいは不当になされる危険性は存在するのであり、法の介入が不要となることはありえない。もちろん、それは医療の質に関わる問題でもある。精神医療が人的にも物的にもさらに充実すれば、リーガルモデルからの要請は、かえって現実から遊離したものとなり、逆に医療の質を低下させる要因にもなるだろう。しかし、精神医療に携わる者の意識が問題となる限りは、法は精神医療の現場に強力に介入せざるをえないのである。

今までの医療一般の根底には、医師たる者は患者に善をなし、害を与えてはならないとする「ヒポクラテスの誓い」がある。何を善となし、何を害となすか、これは伝統的に医師の職業倫理に関わることであるとされてきた。医療は、本来治療を目的とするものであるから、医学上の準則に則って医療技術として正当な方法で行えば足りるのであり、そこに他の判断基準の入る余地はきわめて少なかった。しかし、医学的な効果によって医学的技量が評価される時代はすでに過去のものになりつつある。現代は、医学的な効果だけではなく、さらに医学的措置の妥当性あるいは正当性が医学以外の価値体系から問題とされる時代なのである。 このような流れの根底にあるものは、患者の自己決定権の尊重である。患者が医療を受けるかどうか、またどのような医療を受けるのかは、医師の倫理問題というよりもまさに個人の選択問題なのである(個人の尊厳)。個人の承諾を欠く医療行為(専断的医療行為)を違法とする司法判断はすでに無数に存在し、少なくとも法律家の間では専断的治療行為の違法性については共通の認識となっている。精神医療においても、専断的医療行為が民事上の損害賠償責任の発生根拠とされたり、場合によっては犯罪として処断されうるのである。治療全般にわたって細かなルールを設定している精神保健福祉法では、このことはとくに重要となる。 確かに医療の現場に法が介入しすぎることは、確実に医療の質的低下をもたらすであろう。なぜなら、現場での医学的判断には医師の裁量に委ねられる部分が多いが、医療の方針を決定するものが、医師の技量でも専門家的倫理でもなく、司法的判断であるならば、当該医師としてはその裁量範囲を自己防衛的に判断せざるをえないからである。 問題は、精神病患者は身体の強制的拘束に対して事前の司法審査を受けることができないという、現行法の構造にもあるかもしれない。患者は事後的に都道府県知事に対して、退院ないし処遇改善を請求しうるにすぎず、これが精神医療審査会によって審査される仕組みになっている(法38条の4以下)。行動の自由は最も基本的な基本的人権の一つである。入院に際しての手続の遵守と入院が患者の治療および保護のために必要なものであるのかどうかは、現状では事前の第三者機関によるチェックがない以上、常に精神医療関係者みずからによってチェックされなければならないのである。

今日、インフォームド・コンセントを抜きにして医療を語ることはできない。インフォームド・コンセントに関する研究は活発になされているが、個々の具体的な問題についてはいまだ確固たる原則が確立されているとはいいがたく、インフォームド・コンセントの理念を現実に実現することがいかに困難なことかがいっそう認識されているように思われる。その困難の最たるものの一つが精神医療であろう。素人的に考えても、患者本人が病気であることすら否定し、周囲からの勧めで入院させられ、本人の意思が明確に確認できないまま治療が行われる場合が少なくない精神医療においては、インフォームド・コンセントの理念そのものが問われることは容易に想像できる。精神医療におけるインフォームド・コンセントが、ガンの告知などと同様にデリケートな問題を抱えていることも理解できる。しかし、精神医療と一般医療との同質性・連続性を承認し、精神医療においてもインフォームド・コンセントが至上命題とされる以上は、精神科の診察室が医師と患者との絶え間ない合意形成空間となることが期待されるのである。ただし、これが現状では現場への加重な負担となるとの主張にも理由がある。今回の改正要綱案でもインフォームド・コンセントに関する直接的な規定は置かれていないが、今後、この点についての法改正は必ず必要となるだろう。 【参考文献】
- 松下正明総編集『臨床精神医学講座22巻精神医学と法』(中山書店、1997年)
- 日本医事法学会編『年報医事法学5』(日本評論社、1990年)
- 法学セミナー増刊『これからの精神医療』(日本評論社、1987年)
- 大谷實著『精神保健福祉法講義』(成文堂、1996年)
- シンポジウム「インフォームド・コンセントと精神医療」『法と精神医療』第10号1996、21頁以下
- 平野龍一著『精神保健と法』(有斐閣、1988年)
- 町野朔『患者の自己決定権と法』(東京大学出版会、1986年)
- 厚生省精神保健福祉法規研究会監修『精神保健福祉法詳解』(中央法規、1998年)など