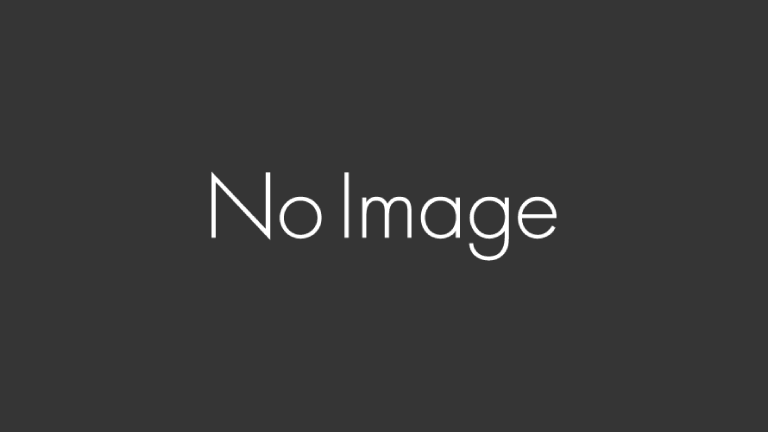組織暴力犯罪とは、 一定の集団によって行われる暴力的犯罪および集団的・暴力的な威嚇を背景にして行われる犯罪のことであるが、 わが国の場合には、 いわゆるヤクザ組織から一部右翼団体や過激派組織による暴力犯罪までを含めることもあり、 組織暴力犯罪の実態はさまざまである。 しかし、 一般には、 組織暴力犯罪とはいわゆる組織暴力団によって行われる犯罪として理解されている。
「暴力団」という言葉は、 「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」(暴力団対策法第2条第3号)と定義されているが、 一般には、 いわゆるヤクザ(博徒)集団と同様の意味で使われてきた。 ヤクザ組織自体は歴史的には古く、 江戸時代後期にまで遡ることができる。 現代でも、 構成員相互で親分・子分・兄弟分の縁(擬制血縁関係)を結び、 江戸時代の任侠道やヤクザ道などを標榜している団体も多く、 断指や刺青、 仁義など裏社会にのみ通用する独特の副次文化がなお残っており、 このような特殊な精神構造からもその問題の根はかなり深い。
暴力団は、 社会経済情勢の変化に伴って、 その組織や活動形態を変化させてきた。 昭和20年代は、 終戦直後の社会的混乱から、 すでにそれまでに存在していた博徒・的屋といった暴力集団にさらに愚連隊と呼ばれる青少年不良集団が加わり、 闇市等の利権を巡って対立抗争がくりかえされた。 昭和20年代後半になり、 社会的経済的秩序が回復するとともに、 弱小の団体が淘汰され、 暴力集団の再編が始まった。 それまでは活動形態や収入源によって区別されていた暴力集団が、 覚せい剤やパチンコの景品買い、 芸能興行など、 大きな利益を生む新たな利権に群がるようになり、 各種の暴力集団の境界があいまいになっていった。 暴力団という呼称が社会に定着したのもこの頃であった。 昭和30年代後半になると、 さらに暴力団の淘汰が進み、 他団体との抗争において優位に立った一部の暴力団が、 その組織力と安定した資金源を背景に地方に進出するようになり、 その過程において大規模な抗争を繰り返し、 弱小の団体をさらに吸収してその勢力を一層拡大していった。 昭和40年代になると、 暴力団に対する社会的関心も強くなり、 警察の集中取締まり(頂上作戦)が展開され、 首領・幹部を含む構成員が大量に検挙されたが、 昭和40年代後半には、 服役していた彼らが相次いで出所し、 組織の復活・再編が図られた。 しかし、 警察の取締まりが強化された結果、 非合法的資金源にのみ依存していた中小の暴力団は壊滅的打撃を受けたものの、 傘下団体からの上納金制度を確立した大規模な暴力団は、 中小暴力団を吸収し、 さらに大規模な広域暴力団へと組織化・系列化が進んだ。 昭和50年代以降、 暴力団の寡占化傾向が一層進み、 一部暴力団は海外にその活動の場を求めていった。 また、 最近では「企業舎弟」や「経済ヤクザ」といった新しい言葉も生まれている。 企業舎弟とは、 「暴力団の影響下にあって企業の形をとって活動するメンバー又は組織」のことであり、 表面的には合法的企業活動を行いながら、 裏で暴力団幹部と結びつき、 暴力団を資金面で支える存在となっている。 また、 経済ヤクザとは、 非合法活動で巨額の利益を得た暴力団が、 合法的企業を装い組織化された経済犯罪を行う集団である。 これらは従来の「暴力団」という言葉ではとらえきれない面をもっており、 暴力団の変貌した姿が新たな問題となっている。 現在、 暴力団の推定年間収入は1兆数千億円といわれ、 その大半は非合法手段によるものである。
平成4年末現在における暴力団構成員の数は、 約56,600人であり、 準構成員を含めると90,600人となる。 このうち二つ以上の都道府県にわたって組織を有する広域暴力団で、 警察庁が集中取締りの対象としている山口組・稲川会・住吉会の3団体に所属する暴力団勢力(構成員および準構成員)は約58,400人であり、 暴力団勢力全体の64.5%にも及ぶ。 この数字からも、 とくに大規模な広域暴力団による寡占化の傾向が進んでいることが分かる(平成5年版犯罪白書181頁)。
暴力団勢力が全検挙人員中に占める比率は、 驚くほど高い。 主要刑法犯に関しては、 脅迫(66.9%)、 賭博(49.2%)、 恐喝(38.8%)、 傷害(22.4%)、 殺人(21.7%)、 暴行(21.2%)等となっており、 特別法犯に関しては、 競馬法(56.4%)、 自転車競技法(48.5%)、 覚せい剤取締法(44.0%)、 児童福祉法(40.2%)、 銃刀法(34.5%)、 職業安定法(27.6%)、 売春防止法(16.1%)、 麻薬取締法(15.1%)等となっている(平成5年版犯罪白書183頁以下)。 このような数字からは、 暴力団がわが国の犯罪の主要な供給源となっているといえよう。
組織暴力団員による犯罪は、 以前は暴力的な犯罪が大部分を占めていたが、 最近ではこの種の犯罪は減少する傾向にあり、 覚せい剤や麻薬等の非合法な物品の販売、 あるいは売春や賭博、 のみ行為等の非合法なサービスの提供に変わってきている(ただし、 彼らの行為から暴力的要素がなくなったわけではない)。 さらに、 政治活動や社会運動を仮装して企業をターゲットとして違法に利益を図る企業対象暴力事犯や、 交通事故の示談、 不動産をめぐるトラブルや債権取立等の市民の日常生活や経済生活に介入して、 違法に利益を図る民事介入暴力事犯も増加している。 これは、 この種の行為が大きな利益をもたらすこと、 また、 暴力団の周辺にこれを利用して利益を得ている国民層が存在すること、 さらにこれらの犯罪が顧客の需要があって始めて成り立つものであり、 被害が発生しにくく、 発覚もしにくいといったような事情があるからである。 このため、 各集団が同じ利益に群がろうとする結果、 暴力団同士の資金源をめぐる抗争が激化している。 ちなみに、 暴力団対策法(後述)が成立した平成3年以降においては、 それまで30件前後であった抗争事件が大幅に減少したが(平成4年は12件)、 けん銃の押収数は平成4年は(改造けん銃を含めて)1,072であった(平成5年版犯罪白書181頁以下)。
不法な利益追求集団の色彩を強く帯びてきた最近の暴力団に対しては、 検挙率や起訴率、 実刑率を高め、 犯罪を行うことによるリスクを大きくすることが重要である。 平成4年度の数字を見ると、 暴力団関係者の起訴率は77.2%であり、 検察庁全既済人員についての起訴率61.9%を大幅に上回っている。 また、 暴力団受刑者は、 全受刑者の28.7%である。 しかし、 B級施設におけるそれは39.8%とかなり高率になっており、 刑務所管理運営上の特別な配慮も必要となっている(平成5年犯罪白書105頁以下)。
暴力団受刑者の処遇においては、 適切な職業に就くことが社会復帰の重要な条件であると考えられることから、 職業指導・訓練がとくに重要視されるべきである。 また、 交遊関係や居住環境等の調整・改善を図るなどして、 本人に対して組織からの離脱を働きかけることも重要である。 これらの処遇は、 構成員歴が浅い受刑者に対してとくに強力に実施されるべきだろう。 なぜなら、 暴力団組織とは、 構成員が犯罪歴を重ねるにしたがって地位が上昇し、 それにつれて多くの違法な利益を手にすることのできる組織であり、 そうなると離脱が一層困難となることから、 早い段階で離脱の条件を整える必要性が認められるからである。
(a) 暴力団犯罪の対策として最も困難なことは、 暴力団組織の内部においては、 犯罪を重ねることによってその者の組織内での地位が上昇するという、 犯罪促進的な秩序が出来上がっていることである。 受刑による一般社会生活上の不利益・不名誉は、 彼らにとってそれほど重大な問題とはならない。 しかし、 暴力団構成員とくに首領・幹部の検挙が組織自体には大きな痛手となるのであるから、 警察による継続的な取締まりが暴力団犯罪に対する有効な対策であることは明らかである。
また、 組織自体の存続基盤を揺るがせるためには、 資金源の根絶と構成員の補充を絶つことも必要である。 資金源の根絶については、 警察のみの力では不十分であり、 税務署をはじめとする諸官公庁や市民の協力が必要である。 また、 一般市民もとくに民事的なトラブルに際して安易に暴力団を利用することをやめなければならない。 暴力を利用する者は、 いずれ同じ暴力の被害者にもなりうるのである。
新たな構成員の補充を絶つことも重要である。 非行集団が暴力団の主要な人的資源となっているが、 このことは非行に対する対策もまた暴力団対策としても機能することを意味している。暴力賛美の風潮を改め、 反社会集団に対する憧れを打ち消さなければならないが、 これも警察的規制や行政的規制以前に、 現代社会的が抱えるさまざまな矛盾を解消することが重要であるだろう。
暴力団構成員の組織離脱を促進し、 彼らの社会復帰を援助することも重要である。 彼らが組織から離脱する主な要因としては、 警察の取締まりおよびそれによる経済的影響、 首領・幹部の検挙、 それによる組織それ自体の解散・壊滅などであるが、 組織離脱がそのまま彼らの社会復帰に直結するものではない。 社会復帰に成功するためには、 合法的職業に就き、 安定した収入を得られること、 組織暴力団との関係が絶縁されること、 家族をはじめ一般社会から受け入れられることなどが必要である。 したがって、 就職の斡旋や職業訓練、 生活環境を整えるための援助や保護などが必要である。
(b) 戦後における暴力犯罪に対する主要な法規制としては、 (1)暴行罪・脅迫罪の法定刑の引き上げ、 暴行罪の非親告罪化、 (2)証人威迫罪の新設、 いわゆる輪姦の非親告罪化、 凶器準備集合罪の新設、 銃砲刀剣類等所持取締法の制定、 (3)暴力行為等処罰に関する法律の部分的な刑の引き上げなどである。 これらの法規制は、 暴力団犯罪に対して一定の効果をもたらしたが、 必ずしも十分なものとはならなかった。 それは、 従来から暴力団の主要な資金源として、 寄付・用心棒代・不当融資・示談介入・債権取立などがあり、 彼らはこれらの行為を行うに際して、 直接暴力を行使するよりも、 表面的には穏やかな交渉や取引の形をとって行っていたために、 それらを明確に犯罪行為としてとらえにくかったからである。 さらに、 暴力団の寡占化傾向が進み、 暴力団が強大になってくると、 彼らは「○○組」といった暴力団の名前を告げるだけで相手方を威嚇することができ、 明確に脅迫や恐喝等の犯罪にならない方法で資金獲得活動を行うことがより容易になったのである。 また、 巨大な組織ほど下部組織からの上納金が多く、 上部組織は自らの手を汚すことなく、 莫大な利益を手にすることもできる。 そこで、 上記のようないわば灰色ゾーンにある行為を禁止の対象とし、 暴力団の資金源を根元から絶つ必要があること、 また暴力団員の離脱を促進するような援助を行う必要があることなどから、 平成4年3月に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(いわゆる暴力団対策法)が施行されたのであった。
暴力団対策法の基本的な構造は、 次のようなものである。 (1)本法は、 すべての暴力団を規制対象としているのではなく、 特定の暴力団を指定し(指定暴力団)、 その暴力団員(指定暴力団員)に対して必要な規制を行う。 (2)指定暴力団員が指定暴力団等の威力を示して行う、 不当寄付金要求行為や不当地上げ行為、 利得示談介入行為などの典型的な不当要求行為を禁止する。 さらに、 指定暴力団員による指定暴力団等の加入勧誘行為、 指定暴力団の事務所等において付近住民に不安を与えるような一定の行為を禁止する。 (3)上記の禁止行為には措置命令を発することが可能であり、 さらに対立抗争時には指定暴力団事務所の使用制限を命じることもできる。 これらの命令違反に対しては罰則が設けられている。 (4)被害回復等のための援助に関する規定、 暴力追放運動推進センターの指定に関する規定などが置かれている。
暴力団対策法施行後の状況は、 次の通りである。 平成4年中に、 山口組・稲川会・住吉会をはじめとする15団体が指定暴力団として指定された。 平成4年中の暴力的要求行為に対する中止命令の数は241件であり、 暴力団の解散・壊滅は、 平成2年には80組織(1,131人)、 3年には131組織(1,430人)、 4年には158組織(2,051人)と急増している。 また、 暴力団勢力は約96,000人と前年と比べてほぼ横ばいであるが、 暴力団構成員は約7,200人減少し、 約56,000人となっていることから、 暴力団構成員の組織離脱あるいは暴力団自らによる構成員の整理が行われたことがうかがえる。 したがって、 暴力団対策法が、 暴力団に対してかなりの動揺を与えたものと評価することができる(平成5年警察白書79頁以下)。 しかし、 暴力団対策法の具体的な内容については、 基本的人権との関連においてなお問題のあることが指摘されている。
(a) 昭和42年頃から全国で学園紛争が多発し、 一部の学生を主体とした集団的暴力事件が頻発するようになったが、 昭和45年頃から学園が一応正常化するとともに、 この種の事件も減少傾向を示した。 しかし、 その後、 「革命」のためには暴力をも否定しないという過激な考えをもつ一部の者たちによって、 飛行機乗っ取り事件、 交番や銀行襲撃事件、 リンチ殺人事件など凶悪な暴力的集団犯罪が起こり、 その手段も自動点火式火炎ビンや劇薬、 手製小型爆弾などが使用されるようになり、 彼らの活動が凶悪なゲリラ的破壊活動へとエスカレートしていった。
過激派集団によるゲリラ事犯は、 平成4年は46件発生しており、 その対象も、 自衛隊関連施設、 鉄道施設、 民間企業の施設、 神社、 個人宅など多方面に及んでいる。 とくに平成4年は個人宅を狙ったものが18件あり、 その手段も時限発火装置や爆発物等を使用した事犯が増加するなど、 悪質化している(平成5年犯罪白書212頁)。
(b) 過激派犯罪の特徴としては、 (1)犯罪そのものが暴力的であり、 集団的・組織的かつ計画的に行われ、 その動機には一応彼らなりの政治的思想性があること、 (2)犯罪が思想ないし価値観によって支えられているために、 犯罪遂行に使命感が持たれていること、 (3)過激なまでの反体制・反権力的な行動がとられ、 現代社会への強い反発・不信感が存在していることなどである。
以上のような過激派犯罪の特徴から、 彼らは基本的にいわゆる矯正処遇の対象とはなりえないとの考えもありうる。 しかし、 政治的動機の問題とは別に、 民主主義を暴力的に踏みにじった責任は問われるべきであって、 殺人や傷害・放火・強盗等の社会侵害行為それ自体を非難し、 それに相応しい刑罰を執行すべきである。 また、 過激派犯罪対策として治安機構の強化や治安立法といったような権力的対応がなされるならば、 それは毒をもって毒を制するということであり、 その副作用の大きさにつねに留意すべきであろう。