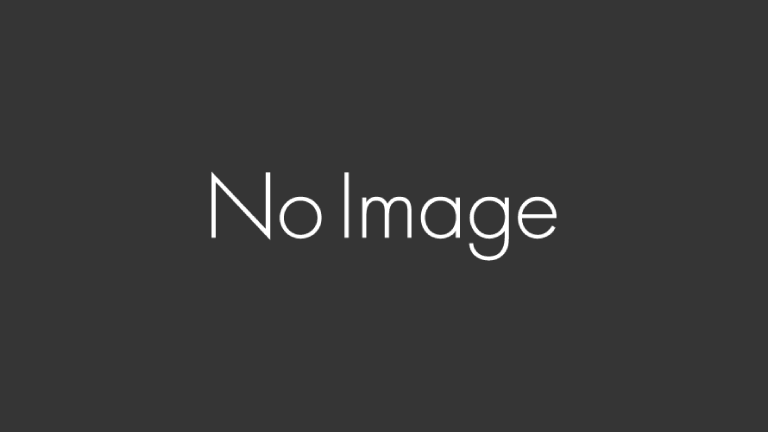罪刑法定主義
刑法は、犯罪という重大なルール違反に対して、刑罰というもっとも厳しい制裁を科すことによって社会秩序の維持をはかるものです。刑法が具体的に適用されることによって、犯罪が認定され、国家の刑罰権が具体化していきます。
刑法が適用される前提としては、まず、そこで用いられている言葉の意味が明確であることが必要です。条文の意味が不明確であれば、適用のしようがありませんし、国民の側から言っても、安心して行動することができません。適法だと思って行動して、後から実はお前の行為は犯罪だったんだと言われてはたまりません。
したがって、何が犯罪となり、それに対してどのような刑罰が科せられるのかということは、明確に法律で規定されている必要があります。この原理を罪刑法定主義といいます。法律の専門用語というのは難しい言葉が多いのですが、この言葉は大変うまくできています。だれが名付けたのかは知りませんが、文字を見ただけでその内容が分かりますね。
条文の解釈
ところで、犯罪と刑罰とを明確に法定するといっても、犯罪の現実的な形態は千差万別です。その一つひとつを具体的に法律で明確に規定するといっても法技術的には不可能ですし、ナンセンスです。そこで、法律の規定というものは、どうしても抽象的にならざるをえません。
たとえば、電車の中で他人の財布をスリ取る。他人の留守宅に忍び込んでお金をとる。店員の目を盗んで店のものを失敬する。犯罪とされるものを個別具体的に明確に規定するのが望ましいならば、そのような行為を一つひとつ条文を設けて処罰することになるでしょう。しかし、それは不可能ですし、ナンセンスです。これらの行為に共通するものは、いずれも人の知らない間に、人の物を自分のものとするということです。刑法は、この共通項に着目して、それを「他人の財物を窃取した」(235条)という形でまとめたわけです。したがって、この条文を実際に適用するにあたっては、まず、その条文の意味するところを解釈して意味を確定しなければなりません。「他人」とは何か、「財物」とは何か、「窃取」とは何か・・・・・・、といったような具合です。
解釈といっても、特別なことをするわけではなく、基本的には古典や漢文の解釈と同じことです。その言葉が本来どのような意味をもっているかを確定するわけです(文理解釈)。その言葉が本来もっている意味の範囲を逸脱することは許されません。また、純粋に文法的な問題と違って、語句の意味を解釈する場合には、常にその語句が用いられた事実的な関連性を忘れてはいけません。
類推解釈の禁止
言葉が本来もっている意味を逸脱してはならないということは、非常に重要なことです。たとえば、刑法のある条文はXという言葉を用いて、ax、bx、cx・・・・・・という行為を禁止しているとします。しかし、これらの行為と事実としては非常に似ているay、by、cy・・・・・・という行為については直接の規定がありません。本来ならば、ay、by、cy・・・・・・という行為を処罰するには、新しくYという条文が必要なんですが、この場合事実として似ているということで、それらの行為にXという条文を適用することを類推解釈(るいすいかいしゃく)といいます。
類推解釈も一般的には法解釈の一つの技術ですが、刑法の世界では決して許されることではありません。解釈といっても、その実体は新たな犯罪類型の創設なのです。一例をあげて、このことを説明しましょう。
明治24年、日本国中を震え上がらせた事件が発生しました。ある巡査が、訪日中のロシア皇太子を殺害しようとしましたが、未遂に終わりました。大津事件です。このようなきっかけで戦争が始まった例は、歴史上いくらもあります。新生日本の明治政府としては、ふとんをかぶってふて寝でもしたい心境であったかもしれませんが、外交的な配慮から、犯人を死刑にすることを考えました。
しかし、当時の刑法では、計画的殺人(謀殺罪)は、死刑に処せられましたが、その未遂は、現行刑法(43条)と違って、必ず減軽することになっており、理論的には死刑を科すことができません。この点に政府は頭を悩ませました。そして、旧刑法にあった、「皇室ニ対スル罪」に着目したのです。
旧刑法では「皇室ニ対スル罪」という独立の犯罪類型が規定されていました。旧刑法の116条では、「天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス」と規定されていたのです。「危害ヲ加ヘントシタル」とありますので、未遂に終わった場合であっても、この場合には死刑を科すことが可能です。ここでいう「皇太子」には、前後の文脈から外国の皇太子を含まないということは明らかですが、政府は、この大津事件の被告人に対して本条を適用するように、裁判官に圧力をかけたのです。これが類推解釈です。しかし、裁判所はこの要求をはねのけ、事件を通常の謀殺未遂として処理し、被告人を死刑とはしませんでした。歴史的には、この事件は司法権の独立を守った事例として記憶されていますが、刑法的に言えば、類推解釈を拒否した重要な事例なのです。
刑法の言葉
今の刑法は明治41年に施行されたものです。とても古い法律なんですね。平成7年に、それまでのカタカナ書きの難解な条文から、口語体に改正されましたが、読みにくい難解な条文も少なくありません。もちろん、刑法の条文の中には、殺人罪の「人を殺した者は」のように、誰にでも分かる条文もあります。しかし、日本語として明確なこの条文も、実際の事例にこれを適用するとなると解釈が必要になります。特に、「人」の意義に関して、最近では難しい問題が生じています。
一般的には、「人」とは生まれてから死ぬまでの人間という意味ですが、たとえば妊娠中の人に対して、母体にはまったく影響を与えずに、薬物等を使って胎児に対してのみ何らかの作用を及ぼし、それが原因となってその胎児が生まれてから死亡したとします。現代の医学では、このようなことは充分に可能です。
この場合、出生後の死亡ですから、「人」が死んだことは間違いありません。そうすると、この場合には殺人罪となるのでしょうか? また、脳の機能が完全に停止しても、器械を使って心臓や肺を人工的に機能させることも可能です。そのような患者に対して、その器械のスイッチを切ればどうでしょうか。やはり、「人」が死亡したとして、殺人罪になるのでしょうか?
このような事例では、まさに殺人罪における「人」という言葉の解釈そのものが問題となっているのです。明治時代の立法者には、このような事態は全く予想されなかったことでしょう。科学が進歩し、それに伴って私たちの生活も意識も変化していきます。法律でもともと予定されていた事実と現実の社会的事実の間のギャップはますます大きくなっていきます。それにつれて、法律の解釈もいっそう困難なものとなっていきます。
目的論的解釈
「人」という言葉は、刑法の他のところにもよく使用されています。たとえば、刑法144条の浄水毒物等混入罪という犯罪にも「人」という言葉が使用されています(「人の飲料に供する浄水に毒物その他ノの健康を害すべき毒物を混入した者は、三年以下の懲役に処する」)。そこで、たとえば、妻が、夫が飲もうとしているコップの水の中に毒物を混入した場合には、本条が適用されるでしょうか。
「人」という言葉そのものの解釈を前提とする限り、文理的には可能です。しかし、本条の罪は、一般公衆の健康を保護することが目的であり(これを公共危険罪といいます)、特定の人の健康を保護しようとするものではありません。特定の人の健康を保護するのは、傷害罪の守備範囲です。したがって、上の事例では、本罪は不成立ということになります。
このように、法規の解釈にあたっては、そこで保護されている利益(これを法益(ほうえき)といいます)は何かということも一つの基準となり、常に他の犯罪との全体的な関連性において解釈されなければならないのです(目的論的解釈)。
上の例は、法文に用いられている語句を、日常的な意味よりも限定的に解釈するという場合ですが(縮小解釈)、場合によっては、拡張して解釈する必要性にせまられることもあります(拡張解釈)。
拡張解釈
判例では、次のような事案が問題となりました。ガソリン・カーの機関手が、運転中に過失でガソリン・カーを転覆させ、多数の乗客に重軽傷を与えました。刑法129条では、過失によって「汽車若しくは電車」を転覆・破壊させる行為が処罰されていますが、立法当時には、ガソリン・カーは存在しなかったために、法文では「汽車若しくは電車」となっています。そこで、裁判では、このガソリン・カーが「汽車」にあたるのか、という点が争われました。そして、裁判所は、ガソリン・カーは汽車である、と判断して、被告人を有罪としました。
学説によっては、この結論を(許される)類推解釈である、とするものもあります。しかし、裁判所が上のような結論を出した背景には、ガソリン・カーは「汽車」と比較して、同じように一定の軌道上を走ることによって多数の乗客を運搬するという点では同じである、という考慮があります。この類似性が決め手です。刑法がこのような犯罪類型を設けた趣旨から言えば、動力が石炭であるのか電気であるのか、あるいはガソリンであるのかということは、この罪の本質的な点には影響がないのです。判決の結論は支持することができるでしょう。
それでは、類推解釈と拡張解釈の限界はどこにあるのか。これは、非常に困難な問題です。抽象的には、国民に対して不意打ちとなるような解釈が類推解釈であるというほかはありません。つまり、拡張解釈は、法が本来予定する範囲内での目的論的解釈であって、類推解釈は、その範囲を越える事実に対して、法の妥当性を認めることなのです。その限界は確かに困難ですが、法の趣旨・目的あるいは法文の論理的な構造などを総合的に判断して決定されることなのです。
要するに、処罰される側に立って、このような行為ならば処罰されないだろうという、国民の予測可能性を奪うような解釈は許されるされるべきではないというべきでしょう。したがって、さきほどの例で言えば、ガソリン・カーを「汽車」に含めて解釈することは許されますが、バスを「汽車」に含めて解釈することは許されない解釈といえるでしょう。