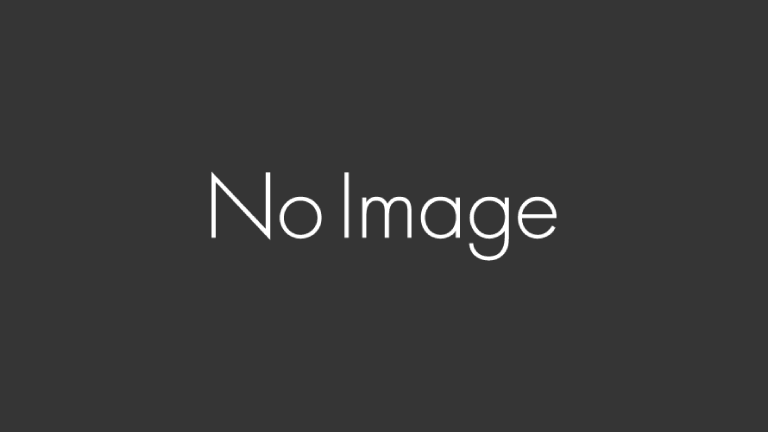ナイフで胸を刺されたBの死体が発見される。
これは、人間の死に方としては、きわめて不自然な死に方ですが、ただそれだけでは何らの刑法的な問題は生じていません。発生した事実が「犯罪」として認定されることが問題の出発点です。いかなる事実も、何びとかによって犯罪として認知されなければ、刑法の世界とは無関係な事実にとどまります。右の場合は、一見して犯罪事実であることが明白ですから、このような場合には、それを発見した人は、通常であれば110番通報を行うでしょう。ここからBの死という事実が、刑法的な事実となります。
犯罪が発生した場合、観念的には国家の刑罰権が発生しているとみることができますが、上で述べたように、法は国家の刑罰権を具体化するためにさまざまな制約をもうけ、いろいろな段階的な手続をへて犯罪(者)が認定されていくわけです。
犯罪とかかわる第一の公的機関は警察です。110番通報などはもっとも有力な捜査のきっかけであり、ここから警察の「B殺人事件」についての捜査が開始されます。刑事訴訟法189条2項には、警察は「犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」、とあります。そのBの死体が犯罪によるものであるという警察の認定が先行しています。
警察は、捜査を続けていく過程でさまざまな証拠を収集し、犯罪を犯したと疑うに足りる人物として、Aという人物を特定しました。警察は、逮捕状によって強制的にAの身柄を拘束することも許されます。
このようにして、捜査が開始されるわけですが、現実問題として犯人のすべてを逮捕し、すべての事件を解決することは不可能ですし、また、警察に知られない事件というものも無数に存在しえます。
したがって、犯罪数というものは、常に認知件数としてしか把握できません。しかし、この認知件数は、そのまま警察の活動状況を示すものとして非常に重要な数字となります。
毎年、法務省から「犯罪白書」という統計書が出されていますが、これを見ると、最近のわが国における刑法犯認知件数は200万件ほどで、検挙率(認知件数における検挙件数の割合)は、数十パーセントほどです。つまり、100件のうちで半分は未解決の事件があるということですが、殺人や強盗などのいわゆる凶悪犯の検挙率は高く、世界的に見てもよい方です。
さて、警察における捜査が終了しますと、事件は一部の例外を除いてすべて検察庁に送られます。ここで「B殺人事件」は、検察官の手によって捜査されます。捜査が終結すれば、検察官はその事件を起訴するかどうかを決定しなければなりません。
国によっては、犯罪の嫌疑がある場合には必ず起訴しなければならないと定めているところもありますが(起訴法定主義)、日本の場合は有罪の証拠がそろっている場合であっても、検察官の裁量で起訴しなくてもよいことになっています(起訴便宜主義)。「B殺人事件」では、Aの「性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況」(刑事訴訟法248条)を考慮して、検察官が起訴するのかどうかを決定します。
検察官が事件を起訴した場合には、検察官は公判を維持して有罪判決を得るための公判活動をしなければなりません。
検察官の公訴提起によって、事件は裁判所に移ります。本件では、検察官がAを殺人罪で起訴しました。それまでは被疑者の地位にあったAは、これ以後は被告人となります。もちろん、この段階ではAはまだ犯罪者ではありません。裁判所がAに対して有罪判決を下し、その判決が確定してはじめて法的にAが犯罪者として処遇されることになります。それまではAは無罪であると推定されます(無罪の推定)。
無罪の推定は近代の刑事裁判における重要な原則です。これがなぜ、刑事裁判における原則なのでしょうか。一般の社会では、常に有罪の推定がはたらいてることを想起してください。刑事裁判において無罪の推定の原則を強調しなければならないとういことは、逆説的ですが、それだけ一般社会においては有罪の推定がなされてる証拠だと思います。
裁判所は、犯罪事実と犯罪者とを決定する最終段階です。裁判には、通常手続と略式手続の二種類がありますが、略式手続とは、軽微な事件に対して一定額の罰金刑を科す簡単な手続ですから、「B殺人事件」の場合には通常手続で審理されます。わが国の刑事裁判では、訴追者と審判者とが分離されています。訴訟は訴追者の訴追をまって開始され、裁判所・訴追者・被告人の三者によって裁判が行われます(弾劾主義)。また、訴訟の追行(主張・立証)は、裁判所ではなく、検察官と被告人(当事者)によって行われ(当事者主義)、訴訟は、検察官と被告人との攻撃・防御の応酬によって進められます。
しかし、背後におおきな組織を有している検察官に比べて、被告人の方は法律的知識も乏しく、その力の差は歴然としています。そこで、被告人の権利を擁護し、その利益を代弁する弁護人の存在が不可欠となります。刑事訴訟法の289条1項には、「死刑又は無期若くは長期三年を超える懲役若くは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない」と規定されていますので、本件の「B殺人事件」の場合には、当然Aに弁護人がつくことになります。
裁判所が犯罪事実を認定する場合には、かならず証拠によらなければなりません(刑事訴訟法317条)。そして、犯罪事実の立証責任は検察官にあり、検察官の主張を否定し、あるいは犯罪の成立そのものを阻却する事実については、被告人側が証拠によって主張します。「B殺人事件」では、検察官がAを殺人罪で起訴したのですから、Aに殺意があったということを、検察側は証拠によって積極的に証明しなければなりません。疑いをかけた人が、その疑いをかけられた人に対して、やましいことがなければ無実であることを積極的に証明してみなさい、というような無茶な論理は通らないわけです。
人の「死」の発生を要件としている刑法上の犯罪はいくつかありますが、本件では、刑法199条の殺人罪と刑法205条の傷害致死罪(「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、二年以上の有期懲役に処する」)とが問題となりました。両罪ともに、客観的には人の死の発生を要件として成立する犯罪ですが、その法律的な意味は大きく異なります。殺人罪が成立するためには、主観的要件として殺人の故意(殺意)の存在が必要ですが、傷害致死罪の場合には、結果的加重犯といって、傷害あるいは暴行という基本犯についての故意で充分であって、重い死の結果については現実に予見していることは必要ないのです。ケンカをしていて、殺すつもりはなかったけど、相手が打ちどころが悪かったために死亡したというような場合が傷害致死罪です。したがって、本件ではAに殺意があったのかどうかということが、実質的な争点となります。
一般に、殺意の認定においては、殺害の部位、用いられた凶器、殺害の動機などが鍵となります。そこで検察官は、Bの殺害に使用された凶器が鋭利なナイフであり、そこにAの指紋が付着していること。また、そのナイフが充分な殺傷能力を有していること。他に数箇所の刺し傷があり、胸の傷が致命傷となっていること。また、BはAの妻と関係があり、そのことでAはBを殺してやると知人にもらしていたこと。Aは日頃から、粗暴な人格の持ち主であったことなどを、証拠をあげて主張します。
これに対して、Aは、次のような主張を行いました。妻の浮気で家庭が破壊され、そのことで話をつけるためにBの帰りを待ち伏せていたこと。決して殺すつもりはなく、ただナイフで脅すつもりであったこと。しかし、Bが突然棒を振り上げて襲いかかってきたので、その場で格闘となり、気がつくとBが死んでいたこと。その後、こわくなって逃げたが、今では大変なことをしてしまったと、深く反省していることなど・・・・・・。
検察側、弁護側双方がそれぞれの主張を行い、それぞれが提出した証拠の取調が行われます。しかし、証拠には信用できないものや、矛盾するものもあります。そのうち、どれを採用するかは、裁判官の自由な裁量にまかされています(自由心証主義)(刑事訴訟法318条)。
また、犯罪事実を認定する場合には、有罪の証拠の方が無罪の証拠の方よりも信用できるという程度の心証では足りず、「合理的な疑いを越える」程度の心証が形成されることが必要です。つまり、被告人が犯罪を犯したということを、あらゆる角度から合理的に疑って、そして、その疑いがすべて否定されるということ、簡単に言えば、裁判官が有罪の「確信」を抱かなければなりません。したがって、その程度の心証に到らない場合には、明白に無実の証明があった場合と同様に、無罪判決が下されることになります(「疑わしきは被告人の利益に」)。
証拠の取調が終了し、検察官の論告・求刑、弁護人の最終弁論などがすむと、裁判所は判決を言渡します。かりに、裁判所がAを有罪とした場合には(なお、殺人についての無罪率は0.2パーセント程度です)、「被告人を懲役○○年に処する」というように、具体的な刑罰の種類と量を決定しなければなりません(量刑)。殺人罪の場合には、刑法199条において、死刑・無期または3年以上の懲役が刑罰として規定されており(法定刑)、これに法律上・裁判上の加重減軽を加えて、処断刑を決定します。この処断刑の範囲内で具体的な刑罰を量定するわけです。そして、このようにして決定された具体的な刑罰を被告人に言渡すことになります(宣告刑)。
以上のようなプロセスをへて、具体的に犯罪事実が認定され、犯罪者が決定されていきます。以下では、このような手続的側面から離れて、刑法そのものの解釈原理について説明します。ここでは、犯罪認定に関する実体法的な制約原理が問題となります。