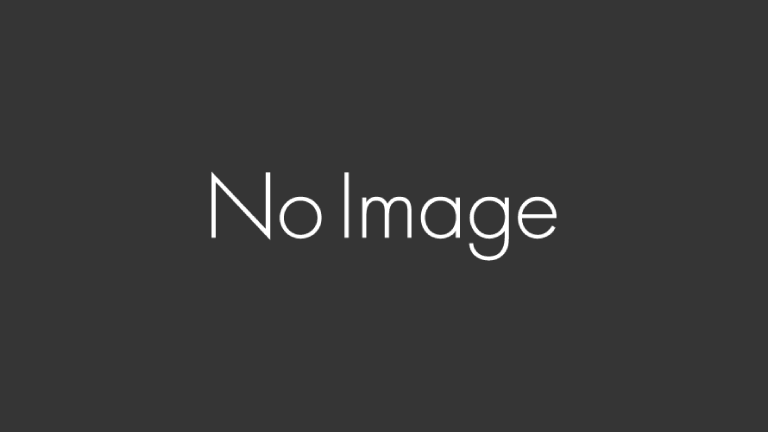これから刑法についての話をしますが、六法全書に載っている法律の中で、刑法はもっとも親しみやすい法律のひとつでしょう。簡単に言えば、刑法とは犯罪と刑罰を定めた法律ですが、「犯罪」という言葉じたい、他の法律用語に比べてそれ以上詳しい説明が必要でないほど、一般の人びとがもつそのイメージは比較的はっきりしています。例えば、刑法の199条には「人を殺した者は、死刑又は無期若くは三年以上の懲役に処する」と書かれており、また、刑法235条には、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する」というよう書かれています。
このような刑法の条文を知らなくても、人を殺したり、他人の物を盗んだりすれば、何かの罰が科せられるということは子供でも知っていることです。また、新聞やテレビで犯罪に関するニュースが取り上げられない日はありませんし、推理小説が好んで読まれたり、映画やテレビドラマでも犯罪はよく取り上げられるテーマです。わたしたちの周囲には、いたるところに「犯罪」があります。
しかし、犯罪とは何かということを、あらためてみなさんに問いかけてみることにします。どのような答えが返ってくるでしょうか。悪い行為、人を害する行為、社会に害を与える行為、犯せば罰が与えられる行為・・・・・・。たしかに、これら回答はいずれも「犯罪」についてあてはまります。しかし、これらの回答は、犯罪についての最も本質的な点を見逃しています。
たとえば、ここに本があります。しかし、「ここに本がある」ということは一体どういうことでしょうか。それは、決して感覚的に目の前の物体を知覚するということではありません。感覚的な知覚にわれわれが「本」という言葉(観念)をあてはめた結果なのです。「本」という言葉を知らなければ、決して目の前の物体が「本」であるということは分からない。それと基本的に同じことが、人の行為についてもいえます。
Aが何らかの理由からBを殺害したとします。「人殺し」です。しかし、人間の行為をとらえる場合には、さまざまな観点からそれを評価することが可能です。Aの行為について、小説家は文学的に、心理学者は心理学的に解明しようとし、法律家は、それを「殺人罪」として評価します。その行為を「犯罪」として評価するのは、あくまでもひとつの側面から見た評価であるにすぎません。
また、ひるがえって考えれば、なぜそのAの行為を殺人罪という「犯罪」として評価できるのかといえば、刑法199条に殺人罪の規定があるからなのです。この刑法の条文が存在しなければ、Aの行為を「人殺し」というように認識できても、殺人罪という「犯罪」としては認識できません。人の行為も、一義的に説明することは不可能であり、それをあらゆる角度からとられることが可能です。
ある行為について、それを「犯罪」として認識するということは、あくまでも刑法というレンズを通して見た事実に対する一つの評価、つまり、刑法の何らかの条文をある事実に適用した結果にすぎないわけです。
ここに刑法と犯罪の一つの関係を認めることができます。以上の点は当然と言えば当然ですが、「犯罪」という言葉の意味を考える場合には、非常に重要なことなのです。
わたしたちの頭の中にはさまざまな概念があります。ひとは、成長の過程でいろいろな概念を学習し、それをさまざまな分類のためにもちいます。その中には、プラスの評価からマイナスの評価まで、無数の価値的な評価も含まれます。その概念あるいは評価基準の複雑な組合せを通じて、わたしたちは世界を眺めているのです。
ところで、「犯罪」あるいは「犯罪者」という言葉も、上に述べたような意味では一つの評価ですが、この言葉はかなりマイナスのイメージが強い言葉であるといえます。それは、一般に犯罪が社会と個人に害を与える憎むべきものであって、刑罰という最強の国家的手段をもちいてまでも排除すべき行為であるというイメージがあるからです。
裁判所がある行為を犯罪として認定すれば、場合によってはその行為者の生命さえをも奪うことが可能となります。刑罰は、犯罪行為に対するひとつの国家的反作用であり、刑罰の厳しさは、裏返せばそのまま犯罪行為の重大性を表しているわけです。
このような意味で、わたしたちは「犯罪」あるいは「犯罪者」という言葉で、有害な事態を表現します。従って、犯罪という言葉には、すでにあらかじめ非常に好ましくないマイナスのイメージが付着しているのです。
現実に刑罰が科せられなくとも、ある人の行為を周囲が「犯罪」と認定する、これはもうそれだけで、その人にとっては致命的なダメージを意味します。それまでにどれだけ社会に貢献し、社会的な地位を獲得した人であっても、いったんその人の行為が犯罪と認定されれば、それまでに得たものすべてを失いますし、その後の人生が大きく左右されます。それほど犯罪という言葉は、強烈な効果をもっているのです。
また、事実が存在しないのに、「犯罪」が認定されてしまうこともあります。このような場合、一般にプラスの評価であれば、それは容易に剥がれますが、マイナスの評価ではそうはいきません。
特に警察などの公けの機関から犯罪の嫌疑をうけて、しかし、後ほど身の潔白が証明されたとしても、犯罪の嫌疑を受けた人は、ただそのことだけで非常に大きなダメージを受けることは間違いありません。公的な機関から、犯罪行為を行った者という烙印が押された場合には、実体はなくてもその烙印は権威をもち、たとえ虚構であっても「リアルな虚構」となります。ヨーロッパ中世における魔女裁判などはその典型ですが、現代においても現実に何十年も無実の罪で苦しんだ人もいます。マイナスの評価を剥がすには、たいへんな努力がいるのです。従って、特に「犯罪」の認定は慎重であるべきです。
犯罪の認定を慎重に行うために、法はさまざまな規制を設けています。どのような行為を犯罪と認定するのかという点については、刑法という法律で規定されていますし、犯罪認定の具体的な手続について、刑事訴訟法という法律で規定されています。
前者の点については、後で刑法の解釈原理として罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)の箇所で説明します。ここでは、一般的に、犯罪がどのような手続をへて認定されていくのかということについて説明したいと思います。