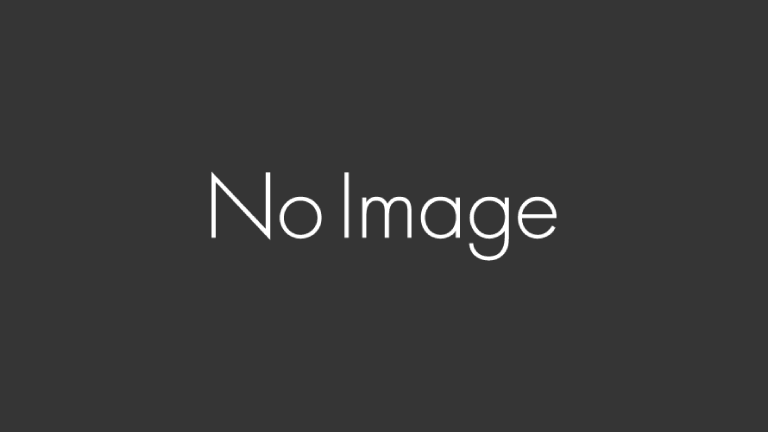中先生の機械嫌いは有名である。逸話は多い。かなり前のことであるが、先生が図書館で文献のコピーを取ろうとされて、本をコピー機の上にそのまま広げられてスイッチを押された。出てきたのは本の背表紙のコピーばかりであった。家の電灯がつかなくなって、いろいろと調べたが分からず、最後に関西電力を呼んで調査してもらったところ、コンセントがはずれていたという話もある。テレビのリモコンはまっすぐに持って、つまり顔と平行に垂直に立てて操作するものだから、発信部が上を向いてしまって何度やっても作動しない。ご家族のお話だと、スイッチが2個以上あるものはダメだったそうだ。したがって、当然ワープロやパソコンも中先生にとっては存在しないに等しい。原稿もすべて手書きである。
今、私の手元に中先生の絶筆となった手書きの原稿がある。テーマは「正当防衛について」であり、これはいずれ何らかの形で公にされることと思う。内容についてここで詳しく触れることはできないが、正当防衛という法現象を国家観の相違にまで遡って根本的に考察した壮大な論文である。この原稿は亡くなられる直前、9月末に完成した。200字詰原稿用紙で1200枚。積み重ねると20数センチの厚みになる。当初、中先生はこれを関西大学法学論集に掲載されるおつもりだった。論集に掲載して欲しい旨の短い手紙と共に、原稿が大学に届いたのが10月5日。しかし、その前日既に入院されていて、入院と同時に危篤状態に陥られた。その後、時折意識が回復したものの、ついに28日未明に息を引き取られた。
中先生が3年前に胃ガンの手術をされ、ご本人もガンの告知を受けておられたことは周知のことである。この3年間はまさに中先生にとって、病との闘いの日々であったことだろう。この手書きの原稿を見ていると、中先生の闘病がいかに壮絶なものであったのかに改めて思いを深くする。
今年(1993年)の4月、中先生は右脇腹に痛みを覚えられ、再度入院された。お見舞いにうかがったら、お元気そうでいつもと変わらぬご様子に安心した。先生は病院のベッドの上にいくつかのドイツ語の論文を広げられ、しきりにノートにメモをとっておられた。「私にはこれしかありませんから」と笑っておられたが、論文に引用した資料の最後の整理をしておられたのだと思う。今になって思えば、その時既にガン細胞は中先生の身体中に広がり、先生の命を序々に浸食していたのだった。中先生は、あらかじめ頭の中で論文の細部までまとめられてから原稿用紙に向かわれるのが常であった。1200枚の原稿というと、普通の健康状態にある者にとっても清書するだけで2ヶ月近くはかかるだろう。実際に執筆にとりかかられたのは、初夏の頃ではなかったか。
先生は独特の癖のある字を書かれるが、几帳面に原稿用紙のマス目を一つずつ埋めて行かれる。原稿を書かれている時は、病のことも何もかも忘れて、理論刑法学の世界に没頭されておられたことだろう。精神現象を含め、すべての生命現象が物質的基礎の上に成立するとしても、この時確かに、中先生の精神は病んだ肉体から乖離し、理論的調和を求めて自由な世界を飛翔していたにちがいない。先生は、いつものように机に向かって、背筋を延ばし黙々と原稿用紙に字を埋めていかれる。さまざまな資料と対話を重ね、刑法理論のもつれた糸をゆっくりとほぐしていかれる。先生にとって最も平和で至福な時間が流れていく。
突然、先生の自由な精神は物質的世界に引きずり落とされる。原稿用紙の23万字目辺りから、雷に打たれたように字が乱れだす。先生の字を読み慣れた者にとっても判読に時間がかかるほどだ。先生の肉体的衰弱・苦悶を、原稿の字が訴える。それは、ぶ厚い鉄板にキリで穴を開けていくような、苦しく辛い作業であったことだろう。
23万字目といえば、おそらく9月上旬のことではないか。ご長男のお話だと、8月から9月にかけての気分の良い日は1日中机に向かわれ、執筆に疲れてくるとそのまま横になり、また気力が満ちてくると起き出して書く。頭の中には、書きかけの論文のことしかない。依頼していた資料のコピーが届くと、また起き出して机に向かう。このような日々であったそうだ。真夏の道にまいた水のように、思想は油断をするとすぐに乾いてしまう。ご自分の頭の中にあるものを、命あるうちに必死の思いで紙の上に固定しようとされていたのだと思う。その姿は、終生学問的真理のみを追求していかれた、学者としての最後の求道の姿勢である。
原稿の最後の頁に中先生は「(完)」という字を記された。先生は万感の思いをもってこの字を記されたことだろう。だが、それと同時に刻苦勉励の人生もまた完結したのだった。Bahnbrecher(先駆者) という言葉を座右の銘とされていた、恩師にいかにも相応しい最期の姿であったと思う。