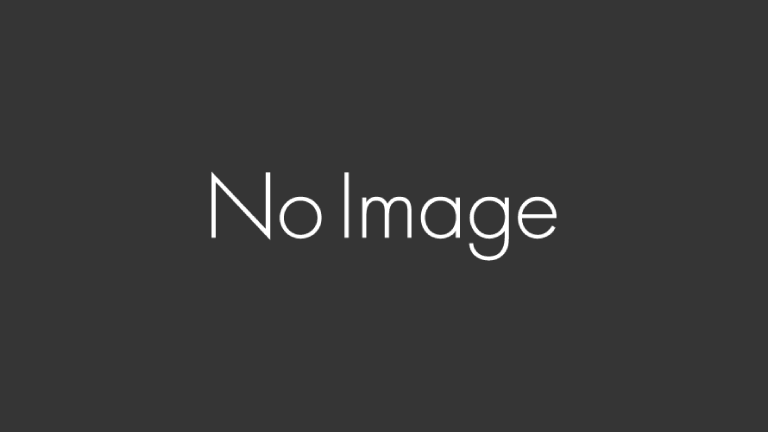人間に意思の自由があるかどうかは、刑法においては特に重要な問題となる。刑罰の基礎は犯された犯罪についてその者に刑法的な責任があるか否かということであるが、刑法的責任とは「あなたはその犯罪を行わないこともできたのだ」ということを前提とするからである。人間の意思にもしも自由がなく、犯罪行為をも含めて人間の行動が物理的法則に従うものだとすれば、犯罪を犯してしまった者に対して、「なぜ、そんなこと(犯罪)をしてしまったのか」という非難は成立しえない。その場合、その犯罪行為はその者にとって制御不可能な必然的現象であって、その原因を行為者の意思に帰することはできない。その意味で、人間の意思が自由であるか否かは、刑法全体の根本問題となるのである。
1 非決定論
意思の自由を主張する見解(非決定論)は、実はわれわれの経験を唯一の根拠としている場合が多い。
人はしばしば岐路に立って迷う。あれかこれかの選択に頭を悩まし、過ぎ去った過去を振り返り後悔する。この後悔という体験こそは、その時の意思決定が自由であったという感覚的記憶そのものの裏返しに他ならない。そして、人間には意思の自由があるというこのような素朴な人間観こそは、われわれの社会にとってのもっとも基本的な了解であると考えられる。それをフィクションと呼ぶか否かは別として、人間社会の諸制度は明らかに自由意思を前提として構築されているのであり、意思の自由は社会のもっとも基本的要素たる「人格」や「主体性」といった概念と深く結びついている。社会は、人間の自由意思を軸としてはじめてその生き生きとした姿を保つことができる。しかし、このような世界観を(同じように社会的に了解されている)自然科学の世界観と調和させようとすると、きわめて困難な事態に遭遇するのである。
2 決定論
宇宙はきわめて微小の粒子から成り、その存在は自然法則(物理法則)の全面的支配下にある。人間の肉体も物理的存在である以上、物理法則の支配を脱することはできない。空を飛びまわる「自由」や何もつけずに水中に長時間とどまる「自由」などは存在しない。さらに、肉体的動作のみならず、感情や意思も究極的には脳内の化学変化であるとすれば、そこからわれわれの意思はすべて因果的・自然法則的に決定されているのだという考えが生ずる。とくに近世以降は、自然現象の法則的説明が世界を記述するための唯一の形式であるとする見解が常識化し、それに伴って自然現象はすべて因果法則によって決定され、必然的に生じるのだという「(機械論的)決定論」の思想が広まった。このような決定論の思想が、地上から天空にいたるまでの一切の物体の運動と状態を説明ないし予知しようとする古典物理学のバックボーンとなっている。
3 決定論に対する疑問
上のような決定論についてはいくつかの疑問が提起されている 。かりに宇宙の究極的法則が発見され、ある瞬間の宇宙を法則的に完全に記述することが可能だとすれば、宇宙の「完全な描写」が何らかの形で物理的構造の中にすでにセッティングされていることになるだろう。そして、その描写が正確であればあるほど、その描写についての描写もまたその物理的存在の中にセッティングされていることになる。つまり、描写についての描写も描写されるべきものの一部を形成していることになる。かくして、世界の描写は入れ子式に無限の連還の中をさまようことになる。このような世界の完全な描写を無限に含む物理的構造というものは、おそらく存在しないであろう。
現代の物理学者で機械論的な決定論に立っている者はほとんどいないだろう。実は、そのような因果観はミクロの世界においては通用しがたいのである。たとえば原子核の放射性崩壊についてである。放射性崩壊においては、原子核が崩壊し、粒子が放出される。崩壊の速度や放出される粒子の数は物質のタイプによって「決定」されている。これは、放射性崩壊そのものが不規則な現象なのではなく、規則的であることを意味する。しかし、個々の原子核のレベルにおいては、その放射性崩壊を決定論的に説明することは極めて難しいとされる。なぜなら、すべての原子核が物質的に同一であるにもかかわらず、その崩壊の時期は全く不確定な現象だからである。これを機械論的な決定論から説明することは困難である。決定論的な法則は、どの原子核に対してもすべて平等に作用するはずだからである。
4 自由という概念
では、粒子のレベルにおける不確定性から人の意思の自由を説くことは許されるであろうか。一見、粒子の振る舞いが不確定的であるという事実は、人間の意思が自由であるとの有力な根拠であるかに思える。しかし、粒子のレベルにおける不確定性は、人の身体のレベルにおける不確定性の存在と直ちに直結するものではない。人の意思が粒子本来の振る舞いを違ったものにすることが可能であったということは未だ証明されていないからである 。不規則であるということがそのまま「自由」であるということではないのである。
では、やはり人間の意思自由は単なる経験的感覚、あるいは幻影にすぎないものなのであろうか。
ここに乱数を発生させる装置があり、それは乱数の末尾が偶数であるならば赤が点滅し、奇数であるならば青が点滅するというようにプログラムされている。その装置は赤くなったり青くなったりするのであるが、誰もそれを見てその装置が「自由」であるとは言わない。しかし、「末尾が偶数であれば赤を点滅させ、奇数であれば青を点滅させよ。」という「ルール(規範)X」が存在し、ある人がそのルールXに従って赤や青を点滅させている場合には、その人を「自由」であると言ってよい場合もあるのである。
先に私は自由という概念は、人間社会における「人格」や「主体性」などといった基本的な概念(制度)と深く結びついているということを述べた。ある人の行為を自由であると述べることは、その人の行為を「人格」や「主体性」といった社会的な概念の中に位置づけることに他ならない。
たとえば新幹線は、物理的には完全に自然科学的な法則に従って動いてる。しかし、午前6時20分新大阪発東京行の「ひかり260号」は、それがかりに車両不良で取り替えられ、物理的な存在としては全く別のものとなっても、あるいは30分遅れで発車しても、依然として「ひかり260号」であることには変わりない。新幹線が物理法則に従っているとしても、それを粒子の運動で説明することは通常の社会的文脈においては全くナンセンスである。「ひかり260号」は、列車運行についての制度、あるいは広く社会的な意味の次元で論じなければならない。そして、犯罪行為の説明に際しても、行為が社会的存在である以上(後述)、物理のレベルにおける決定性や非決定性、あるいは不確定性をもとにして議論することも同様に意味のないことなのである。
5 制度的現実としての自由
人間の意思や認識、行為や実践、これらは一般に考えられている以上に実は社会的文化的に規定されている。それらは、特定の社会構造においてすでに共同主観(社会)化されている。われわれが「自由に」「行為した」と信じているものも、実は社会的文脈においてのことなのである。
たとえば音声言語。物理的なものとしての音声は、人の肉体的構造によってある程度規定されている。人が発する音や生理的に聞くことのできる音には物理的限界がある。しかし、音声が言語として意味をなすためには何よりも文法というルール(規範)が前提とされなければならない。その国の言語をあらかじめ学習しなければ、声帯から発せられる物理的な空気振動を適切に言語として分節化することはできない。つまり、発話という行為が意味をなすためには、それに関係する者に文法というルールがあらかじめ共同的に主観化されていることが不可欠なのである。あえて言えば、ある国の言語を「自由に話せる」状態というのは、個人がその文法的ルールの全面的支配下にあり、そのルールの中に完璧に埋没している状態なのである。
生理的に支配されていると思われる食欲ですら、文化(すなわち共同主観化された制度)の問題である。日本人はタコの刺し身を見て食欲を感じるが、ある民族では食欲どころか嫌悪感すら生じる。われわれがタコを自由な意思によって食したとしても、それは文化的社会的に決定された選択なのである。人は食事という行為を通じて、肉体的生理的欲求を充足させるとともに、「食」にまつわる社会的文化的なさまざまな意味をも消化するのである。このことは(さらに本能的と考えられている)性欲に関してもよく当てはまるだろう(お歯黒の女性にセックスアピールが感じられていた時代もある) 。
このように考えると、自由であるか否かということは、物理的に決定されているか否かということとは別の次元で考えた方がよさそうである。自由とは、(社会的文化的に規定されている)行為の始動者となりうるということである、と定義してみよう。それは、その行為者を「主体性」や「人格」、あるいは「賞と罰」といった基本的な制度のネットワークの中に位置づけることに他ならない。われわれの肉体的動作は不断に他者によって意味づけられ続け、人は何層もの多重的な意味的空間において生きる存在となる。このような意味的空間のいずれかの次元において行為の始動者として他者によって承認される場合に、われわれはその限りにおいて自由であると言える。したがって、同一の人物がある局面では自由であり、他の局面では自由でないとされることもありうるのである(そして、多くの悲劇はここから生じる)。犯罪行為を犯す自由があったか否かも、刑罰が社会的制度である以上、このような多面的な自由を前提とするものでなければならないだろう。